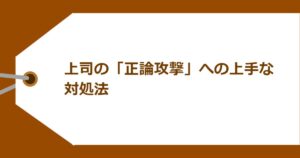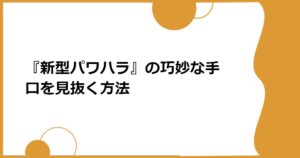「時短ハラ」って何?働き方改革の落とし穴
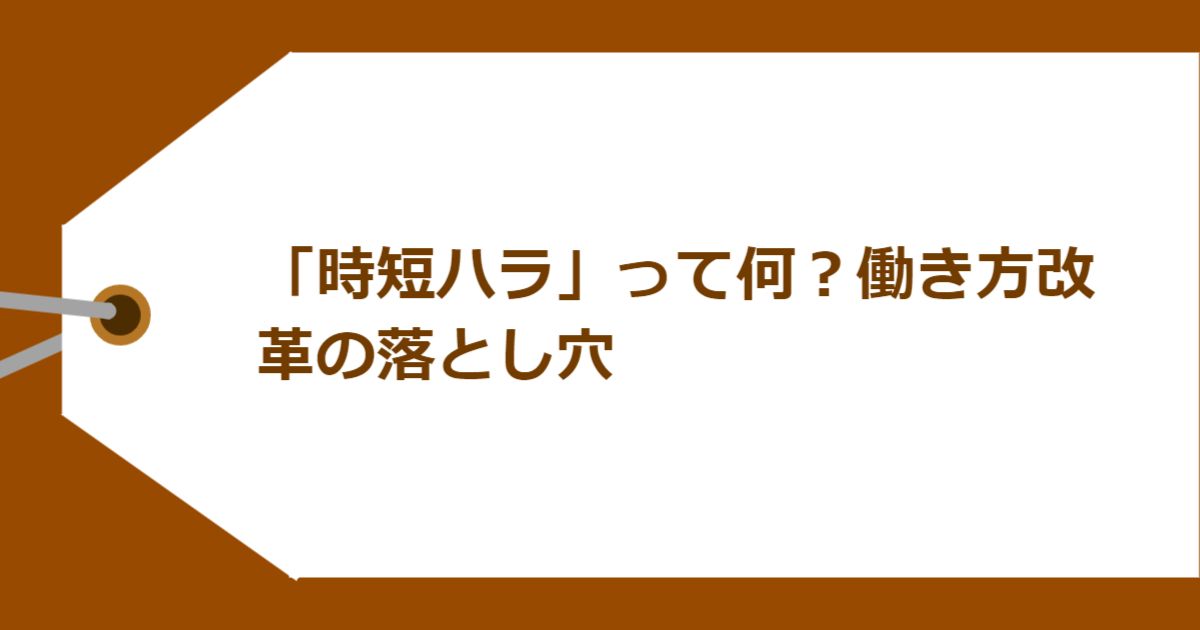
「働き方改革」という言葉を聞かない日
はないほど、企業の労働環境改善が注目されています。
しかし、その陰で新たな問題が浮上しているのをご存知でしょうか?それが「時短ハラスメント」、通称「ジタハラ」です。
「残業は禁止!定時で帰って!」と言われても、仕事の量は変わらない...。
結局、家に持ち帰って作業したり、隠れて残業をしたりしていませんか?これこそが、働き方改革の名の下に行われる新しいタイプのハラスメントなんです。
2018年には「ユーキャン新語・流行語大賞」にもノミネートされ、いまや社会問題となっているジタハラ。その実態を正しく理解して、自分の働き方を見直してみましょう。
時短ハラスメントの正体
時短ハラスメント(ジタハラ)とは、企業が働き方改革を進める中で、業務量の調整や効率化などの具体的な対策を講じることなく、従業員に労働時間の短縮や定時退社を強要するハラスメントのことです。
働き方改革との関係
働き方改革実行計画には「長時間労働の是正」という重要なテーマが含まれています。本来であれば、業務の効率化を図りながら時間外労働を抑制し、ワークライフバランスを整えることが目的です。
しかし、多くの企業では表面的な対応に留まってしまい、従業員に一方的な負担を強いる結果となっています。
ジタハラが生まれる構造
- 業務量は従来のまま
⇒ 仕事の内容や量に変化がない - 時間だけ短縮
⇒ 残業禁止や定時退社の強要 - 具体的な改善策なし
⇒ 効率化や人員配置の見直しを行わない
🔑 ワンポイント
働き方改革の本質は時間短縮ではなく、生産性向上と従業員の健康確保です
ジタハラの典型的なパターン
実際の職場で起こりやすい時短ハラスメントには、次のようなパターンがあります、
パターン1:業務量据え置きでの時短強要
これまで月60時間の残業で処理していた業務を、何の改善策もなく「今月から残業ゼロで」と命じられるケースです。
パターン2:強制的な電源オフ・退社命令
「定時になったらパソコンの電源を切って帰れ」と命令されるものの、翌日までに終わらせるべき業務がある状況です。
パターン3:残業者の名前公開
残業時間が多い社員の名前を社内掲示板に掲載するなど、懲罰的な対応が行われるケースです。
FAQ(よくある質問)
時短ハラスメントの基本について、よくある疑問にお答えします。
働き方改革との関係や具体的な問題点について、理解を深めていきましょう。
適切な時短は業務の効率化や人員配置の見直しを伴いますが、ジタハラは具体的な改善策なしに時間短縮だけを強要する点が決定的に異なります。従業員への配慮があるかどうかが境界線です。
そんなことはありません。真の働き方改革は、業務プロセスの見直し、適切な人員配置、ITツールの活用など、根本的な改善を伴います。単に「早く帰れ」と言うだけでは改革とは言えません。
ジタハラ自体を取り締まる特別な法律はありませんが、2019年に成立した改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に抵触する可能性があります。優越的な関係を背景とした精神的苦痛を与える行為として認定されるリスクがあります。
2017年の調査では、働き方改革に取り組む企業に勤めるビジネスパーソンの約4割がジタハラにつながる悩みを抱えていることが判明しています。「業務量が変わらないのに時間が短くなった」という声が多数寄せられています。
ジタハラが引き起こす深刻な問題
時短ハラスメントは、単なる「時間の問題」では済まない、深刻な影響を職場と従業員にもたらします。
従業員への影響
ジタハラによって最も深刻な被害を受けるのは、現場で働く従業員たちです。
隠れたサービス残業の蔓延
表向きは残業が禁止されていても、実際には
- 自宅への仕事の持ち帰り
- タイムカードを押した後の隠れ残業
- 早朝出社による就業前作業
これらは全て、本来であれば残業代が支払われるべき労働時間です。
精神的な負担とストレス
「定時で帰らなければいけない」というプレッシャーと「仕事が終わらない」という現実の狭間で、従業員は大きなストレスを抱えることになります。
🌈 ちょっと一息
仕事の質の低下や納期遅れは、最終的に会社全体の信頼低下につながります
企業が負うリスク
ジタハラを放置した企業は、様々な法的・経営的リスクを負うことになります。
労働法違反のリスク
- 残業代未払い
⇒ 隠れ残業分の賃金支払い義務 - 労働時間管理義務違反
⇒ 適切な勤怠管理を怠った責任 - 職場環境配慮義務違反
⇒ 安全で健康的な職場環境を提供する義務
人材流出と企業イメージの悪化
優秀な人材が離職し、「ブラック企業」として認識されるリスクが高まります。特に人材獲得が困難な現在、企業の評判は経営に直結する重要な要素です。
FAQ(よくある質問)
ジタハラの影響と対処について、実際に困った時の疑問にお答えします。
被害を受けた時の具体的な対応方法や権利について確認しておきましょう。
会社の指示により自宅で行った作業は、労働時間として認められる可能性が高いです。持ち帰り残業も本来は残業代支払いの対象となります。労働基準監督署に相談することをおすすめします。
直接的な指摘は関係悪化のリスクがあります。まずは人事部門や社内の相談窓口、労働組合などに相談し、組織的な解決を図ることが効果的です。記録を残しながら慎重に対処しましょう。
業務の優先順位を上司と明確にし、「この業務量では定時内に完了が困難」であることを具体的に伝えましょう。改善されない場合は、労働基準監督署や社外の相談機関への相談を検討してください。
ジタハラによる過度なストレスが原因で心身の健康を害した場合、労災認定の可能性があります。医師の診断書と労働実態の記録があれば、労働基準監督署に相談できます。一人で悩まず専門機関に相談しましょう。
健全な働き方改革を実現するには
本来の働き方改革は、従業員の幸せと企業の持続的成長を両立させるものです。ジタハラを防ぎ、真の改革を実現するために必要なポイントを確認しましょう。
企業側に求められる取り組み
健全な働き方改革には、経営層から現場まで一体となった取り組みが必要です。
業務プロセスの根本的見直し
- 業務の優先順位明確化
⇒ 重要度・緊急度による仕事の整理 - 無駄な業務の削減
⇒ 形式的な会議や不要な資料作成の見直し - ITツールの積極的活用
⇒ 自動化による効率化の推進
適切な人員配置と組織体制
業務量に見合った人員配置や、特定の人に業務が集中しない体制づくりが重要です。
働く側ができること
従業員側も、受け身ではなく積極的に改善に参加することで、より良い職場環境を作ることができます。
現状の可視化と提案
- 業務時間の記録
⇒ 実際の労働実態を正確に把握 - 具体的な改善提案
⇒ 現場からの建設的な意見を発信 - チームでの情報共有
⇒ 問題を個人の能力不足として処理せず、組織の課題として認識
🔑 ワンポイント
一人で抱え込まず、同僚や上司との対話を通じて解決策を模索することが大切です
FAQ(よくある質問)
健全な働き方改革の実現について、前向きな解決方法をご紹介します。
個人と組織の両面から、より良い職場環境を作るためのヒントにしてください。
どんな規模の会社でも可能です。重要なのは経営層の理解と現場の声を聞く姿勢です。まずは小さな改善から始めて、従業員が納得できる形で進めることが成功の鍵となります。
多くの場合、上司自身も会社からのプレッシャーを受けており、具体的な改善方法がわからないまま結果だけを求められている状況があります。上司を責めるより、組織全体の問題として捉えることが解決につながります。
化学品製造の東亞合成株式会社では、現場と人事が連携して業務改善を図り、長時間労働を解消しました。重要なのは現場の実情を把握し、従業員と一緒に解決策を見つけることです。
業務の優先順位づけ、集中できる時間帯の活用、不要な会議の削減提案など、個人レベルでも多くの改善が可能です。ただし、根本的な解決には組織全体での取り組みが不可欠です。
まとめ
「時短ハラ」は、働き方改革という、本来は良い取り組みが表面的な対応に終わってしまった時に生まれる。新しいハラスメントです。単に「早く帰れ」と言うだけでは、従業員を苦しめる結果にしかなりません。
真の働き方改革とは、業務の効率化、適切な人員配置、そして従業員一人ひとりが納得できる職場環境作りを通じて実現されるものです。
もしあなたが今、仕事は減らないのに「早く帰れ」と言われて困っているなら、それは決してあなたの能力不足ではありません。一人で抱え込まず、同僚や信頼できる人に相談し、必要に応じて専門機関の助けも借りながら、健全な働き方を実現していきましょう。
働き方改革は、企業と従業員が共に幸せになるための取り組みであるべきです。ジタハラのない、本当の意味での働きやすい職場を作るために、一歩ずつ前進していきましょう。
→ 関連ブログ:『会社の相談窓口が頼りにならない時、どうすればいい?』へ
→ 関連ブログ:『朝起きるのがつらい時、心を軽くする3つの習慣』へ