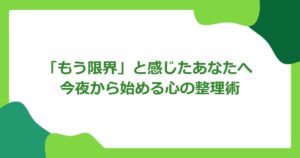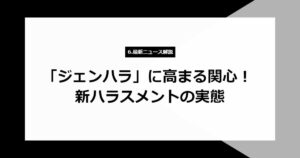会社の「就業規則」でハラスメント対策をチェックする方法
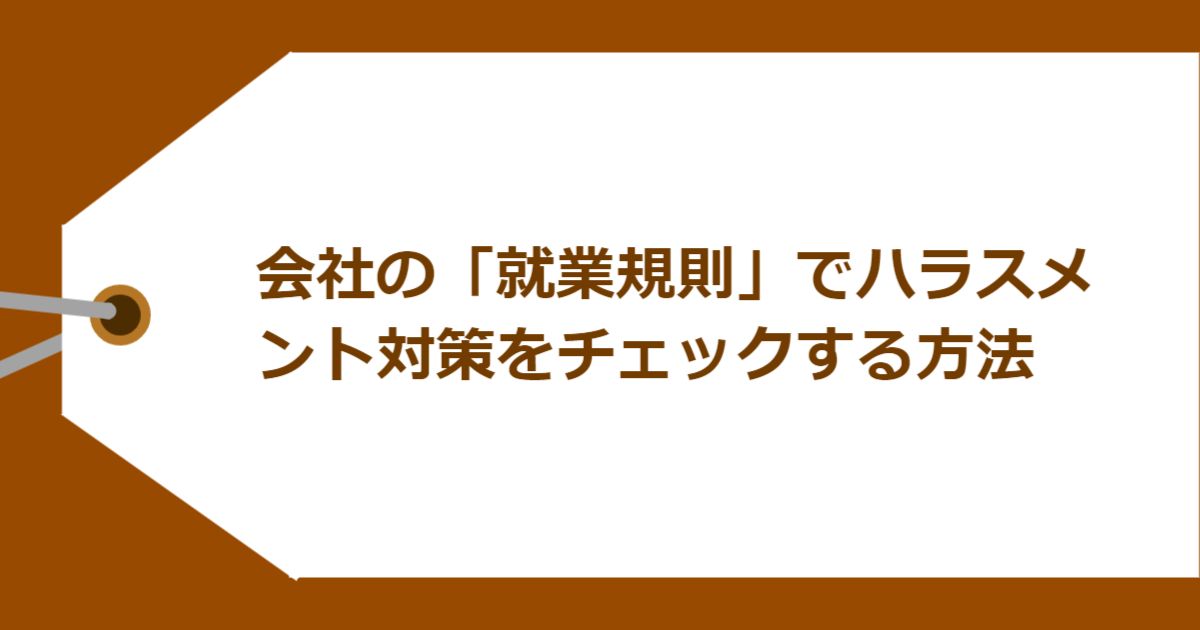
「うちの会社にハラスメント対策ってあるのかな?」
「相談窓口はあるって聞いたけど、どこに書いてあるんだろう?」
そんな疑問を感じたことはありませんか。
実は、あなたの会社のハラスメント対策について知るための一番確実な方法があるんです。
それが「就業規則」を確認することです。就業規則は、会社で働くルールが書かれた重要な文書で、ハラスメント防止に関する具体的な取り決めも記載されていることが多いんです。
でも、
「就業規則なんて見たことない」
「どこで見られるの?」
「何をチェックすればいいの?」
という方も多いはず。この記事では、就業規則を使って自分の会社のハラスメント対策を確認する具体的な方法を、わかりやすく解説します。いざという時のために、今のうちに確認しておきませんか。
就業規則とは?どこで見ることができるのか
就業規則とは、会社が定める「職場のルールブック」のようなものです。労働時間や休憩、賃金の決定方法、服務規律や懲戒に関する事項、そして多くの場合、ハラスメント防止に関する規定も含まれています。
就業規則の一般的な閲覧場所
多くの会社では、労働者が就業規則を確認できるよう、以下の方法で公開しています。
① 総務部や人事部での閲覧
「就業規則を確認したい」と申し出れば、見せてもらえるのが一般的です。コピーをもらえる場合もあります。
② 社内イントラネットでの掲載
社内のイントラネットやポータルサイトに就業規則を掲載している会社も増えています。「規則集」「社内規定」などのページを探してみてください。
③ 休憩室や掲示板での掲示
一部の会社では、休憩室や共用スペースの掲示板に就業規則を掲示している場合があります。
④ 入社時の配布資料
入社時に配布される資料の中に就業規則が含まれていることもあります。入社時の書類を見直してみてください。
🔑 ワンポイント
就業規則が見つからない場合は、直属の上司や総務部・人事部に直接問い合わせてみましょう
就業規則でチェックすべき重要ポイント
就業規則を手に入れたら、ハラスメント対策に関して確認すべき重要なポイントを見ていきましょう。
① ハラスメント防止規定の有無と内容
まず最初に確認すべきは、そもそもハラスメント防止に関する規定があるかどうかです。
探すべきキーワード
- 「ハラスメント防止」「パワーハラスメント」「セクシュアルハラスメント」
- 「職場環境」「人格の尊重」「職場の秩序」
チェックポイント
- パワハラ、セクハラなど、どの種類のハラスメントが禁止されているか
- ハラスメントの定義が具体的に書かれているか
- 単なる「職場の秩序維持」だけでなく、働く人の人格や尊厳を守る視点が含まれているか
② 相談窓口・通報制度の詳細
ハラスメントの相談や通報ができる窓口についての記載を確認しましょう。
確認すべき内容
- 相談窓口の設置場所(人事部、総務部、外部機関など)
- 相談方法(面談、電話、メール、匿名での相談が可能かなど)
- 担当者の役職や連絡先
- 外部相談窓口の有無(弁護士事務所、専門機関との契約など)
- 相談可能な時間帯(営業時間内のみか、時間外対応があるか)
良い相談窓口の特徴
- 複数の相談ルートが用意されている
- 匿名での相談が可能
- 外部の専門機関との連携がある
- 相談者のプライバシー保護が明記されている
③ 調査・対応手順と処分規定
ハラスメントの相談や通報があった場合の、会社側の対応手順についても重要なチェックポイントです。
確認すべき項目
- 調査開始の時期
⇒ 相談からどの程度の期間で調査を開始するか - 調査方法
⇒ 聞き取り調査、証拠収集の方法など - 調査担当者
⇒ 人事部、外部専門家など - 調査結果の報告
⇒ 相談者への報告の有無 - 懲戒処分の種類
⇒ 戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など
適切な処分規定の例
- ハラスメントの程度に応じた段階的な処分が設定されている
- 重大な事案に対しては懲戒解雇も含む厳しい処分がある
- 処分の判断基準が明確に示されている
🌈 ちょっと一息
就業規則は会社との「約束」です。そこに書かれている内容は、あなたが正当に求めることができる権利です
就業規則を活用した自己防衛と注意すべきケース
就業規則を確認した後は、それを実際の自己防衛に活用しましょう。同時に、不十分な規定しかない場合の対処法も知っておくことが大切です。
予防的な活用方法
① 会社の姿勢を把握する
就業規則の内容から、会社がハラスメント問題にどの程度真剣に取り組んでいるかがわかります。詳細で具体的な規定がある会社は、実際の対応も期待できる可能性が高いです。
② 相談窓口の事前確認
いざという時に慌てないよう、相談窓口の連絡先や利用方法を事前に確認しておきましょう。可能であれば、どんな担当者がいるのかも把握しておくと安心です。
③ 同僚との情報共有
職場の仲間と就業規則の内容を共有することで、職場全体のハラスメント防止意識を高めることができます。
注意すべき不十分な規定のケース
以下のような内容だった場合は、会社のハラスメント対策が不十分である可能性があります。
危険信号1:規定が曖昧
- 「職場の秩序を乱す行為は禁止」といった抽象的な表現のみ
- 具体的なハラスメントの定義や例示がない
危険信号2:相談窓口が不明確
- 相談窓口の連絡先や担当者が不明確
- 「上司に相談」程度の記載しかない
危険信号3:対応手順が不透明
- 「適切に対応する」といった曖昧な表現のみ
- 調査期間や方法、処分内容が明記されていない
不十分な場合の対処法
もし自社の就業規則が不十分だった場合は、以下の方法を検討してみてください。
- 労働組合がある場合
⇒ 組合を通じて会社に改善を申し入れる - 人事部への提案
⇒ 他社の事例を参考に、規定の充実を提案する - 外部の専門機関への相談
⇒ 労働局や専門家に相談して、適切なアドバイスを受ける
トラブル発生時の活用方法
① 相談時の根拠として活用
「就業規則の○○条に基づいて相談します」と明確にすることで、会社側も真剣に対応せざるを得なくなります。
② 適切な対応を求める根拠
就業規則に書かれている手順通りに対応されない場合、「規則に従った対応を求める」として改善を求めることができます。
③ 外部機関への相談時の資料
労働基準監督署や弁護士、労働局に相談する際、就業規則のコピーを持参することで、より具体的で有効なアドバイスを受けることができます。
まとめ
会社の就業規則は、あなたを守るための重要な「情報源」です。そこには、ハラスメント防止規定、相談窓口、調査手順、処分内容など、いざという時に必要な情報が記載されています。
就業規則を確認することで、あなたの会社がどの程度ハラスメント対策に取り組んでいるかがわかり、万が一の時にどんな支援を受けられるかも事前に把握できます。また、不十分な規定しかない場合は、改善を求めたり、外部機関に相談したりする際の重要な資料にもなります。
「まだ何も起きていないから大丈夫」ではなく、「いざという時のために今のうちに確認しておく」という予防的な視点が大切です。あなた自身を守るために、ぜひ一度、あなたの会社の就業規則をチェックしてみてくださいね。
→ 関連ページ:『もう迷わない。目的別の最適な相談先マップ』へ
→ 関連ブログ:『会社の相談窓口が頼りにならない時、どうすればいい?』へ