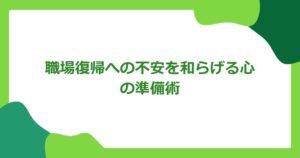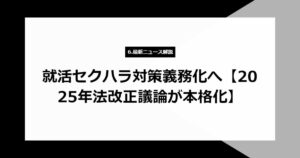労災認定の基準と申請の具体的手順【2025年最新版】
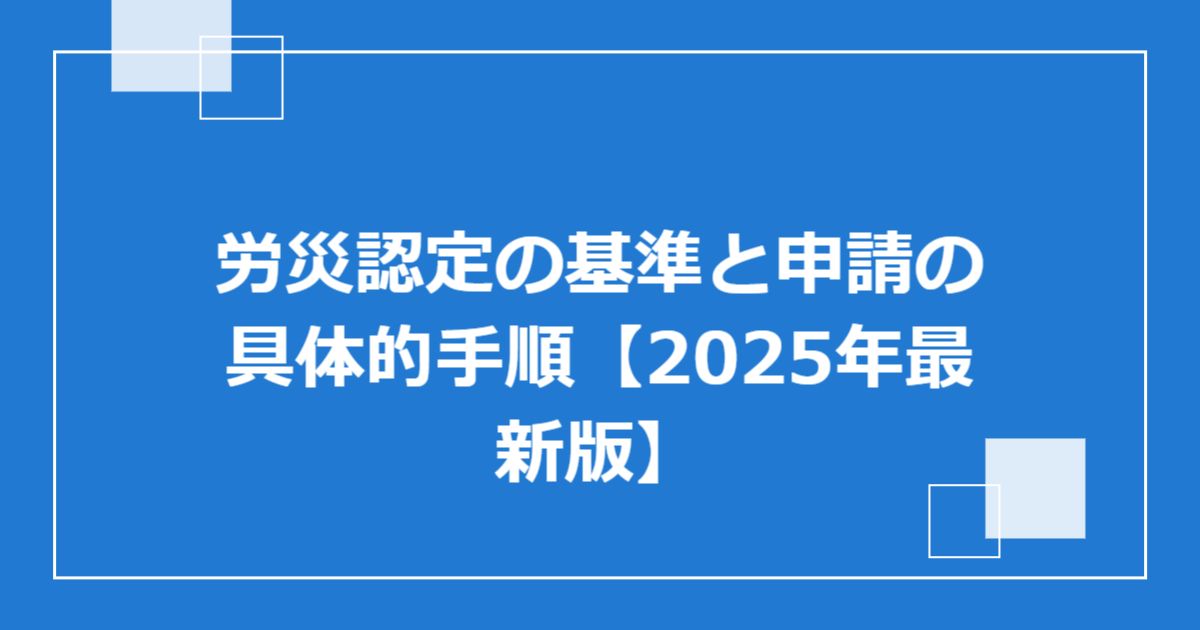
ハラスメントが原因で心身の健康を害した場合、
労災として認定される可能性があります。
「パワハラでうつ病になったけど、これって労災になるの?」
「労災申請って難しそう…」
「会社が協力してくれなくても申請できるの?」
2020年6月のパワハラ防止法施行に合わせて、精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」の項目が新たに追加されました。令和5年度の精神障害による労災認定件数は883件と5年連続で過去最高を更新し、その原因のトップがパワハラという現実があります。
今記事では、ハラスメント被害者が知っておくべき労災認定の基準と、具体的な申請手順について詳しく解説します。
ハラスメントで労災認定される3つの条件
労災として認定されるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1:精神障害の発症
医師によってうつ病、適応障害、心因反応、睡眠障害などの精神障害と診断されていることが必要です。これらの精神障害は、外的要因からのストレスが個人の許容範囲を超えたときに発症すると考えられています。
条件2:業務による強い心理的負荷
発症前のおおむね6カ月間に、業務による強い心理的負荷(ストレス)があったことが求められます。この点については、2023年9月から運用が変更され、従来は専門医3名の合議で認定していたところを、決定が困難な事案を除き、1名の意見で迅速に決定できるようになりました。
条件3:業務以外の要因の排除
業務以外の心理的負荷(家庭内の問題、借金、病気など)や、本人の性格・既往症などが主な原因ではないことが必要です。
「強い心理的負荷」と判断される具体例
2020年の労災認定基準改正により、パワハラによる心理的負荷は以下の3段階で評価されるようになりました。
心理的負荷「強」と判断される場合
労災認定される可能性が高い具体例。
- 身体的攻撃の場合
⇒ 治療を要する程度の暴行を受けた、暴行を反復・継続して執拗に受けた - 精神的攻撃の場合
⇒ 人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた、複数の者により人格を否定する言動が執拗に行われた - 人間関係からの切り離し
⇒ 長期間にわたって別室に隔離されたり、専ら雑務に従事させられた - 過大な要求
⇒ 新人に対して必要な教育を行わずに到底対応できない業務を命じた
心理的負荷「中」と判断される場合
単発では労災認定されにくいが、他の要因と合わせて評価される具体例。
- 人格や人間性を否定するような精神的攻撃(反復・継続していない場合)
- 必要以上に長時間にわたって肉体的負荷の大きな業務を行わせた
- 上司が部下の人格や能力を否定するような発言を行った
重要なポイント:会社の対応も評価対象
中程度のパワハラでも、被害者が会社に相談したのに適切な対応がされず改善されなかった場合は、強度のストレス要因とされ労災認定の対象となります。
労災申請の具体的手順
労災申請は、被災した労働者本人または遺族が行います。会社が協力しない場合でも、自分で申請することが可能です。
ステップ1:必要書類の準備
療養補償給付の場合
- 受診先が労災保険指定医療機関かを確認
- 指定医療機関の場合
⇒ 「5号用紙」を準備 - 指定外医療機関の場合
⇒ 「7号用紙」と医師の証明書を準備
休業補償給付の場合
- 「8号用紙」を準備
⇒ 賃金を受けられない期間が4日以上続いていることが必要
ステップ2:事業主証明の取得
会社に対して事業主証明欄への記載・押印を依頼します。会社が協力しない場合は、証明拒否理由書を提出することで手続きを進められます。
ステップ3:申立書の作成
労災請求書だけでは詳細が伝わらないため、別途「申立書」の提出が求められることが多くあります。申立書には以下の内容を具体的に記載します。
パワハラが発生した日時・場所・状況
- 加害者の氏名・立場
- 具体的な言動の内容
- 目撃者の有無
- 会社への相談経緯と対応
- 精神的・身体的影響
ステップ4:証拠の収集と提出
以下のような証拠を可能な限り集めて提出します
- 音声録音データ
- メールやLINEのやり取り
- 医師の診断書・カルテ
- 業務日報や勤怠記録
- 同僚の証言
- 日記やメモ
ステップ5:労働基準監督署への提出
管轄の労働基準監督署に必要書類を提出します。精神障害の場合、審査には数カ月から1年程度かかることがあります。
🔑 ワンポイント
労災申請には時効があります。療養給付は療養費支出日の翌日から2年、休業補償は賃金を受けられない日の翌日から2年です
会社が協力しない場合の対処法
労働者には労災申請をする権利があり、会社はその手続きについて助力義務があります。しかし、実際には会社が協力しないケースも少なくありません。
事業主証明を拒否された場合
- 証明拒否理由書を労働基準監督署に提出
- 労働者自身で必要事項を記載して申請
- 労働基準監督署が会社に直接確認
会社が意見書を提出する場合
会社がパワハラの事実を否定する意見書を提出することがありますが、これによって申請が却下されるわけではありません。労働基準監督署は中立的な立場で事実関係を調査します。
まとめ
ハラスメントによる精神障害の労災認定は、2020年の基準改正により申請しやすくなりました。年々精神障害による労災申請件数は増加傾向にあり、2023年度では3,575人中883人が労災補償の支払いを受けています。
労災認定を受けるためには、精神障害の発症、業務による強い心理的負荷、業務以外要因の排除という3つの条件を満たす必要があります。特に重要なのは、パワハラの具体的な状況を詳細に記録し、適切な証拠を収集することです。
会社が協力しない場合でも、労働者自身で申請することは可能です。ただし、申立書の作成や証拠の整理は専門的な知識を要するため、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
労災認定は、治療費の負担軽減だけでなく、ハラスメント被害の事実を公的に認定してもらう重要な手続きです。諦めずに適切な手順で申請を進めていきましょう。
→ 関連ページ:『正当な権利『労災申請』で心と生活を守るための全手順』へ
→ 関連ブログ:『心が疲れた時、知っておきたい「傷病手当金」のこと』へ