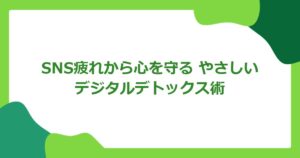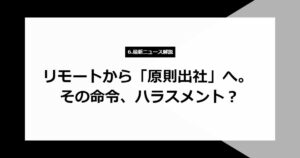退職後の住民税に驚愕…「忘れた頃に来る請求」に備える方法
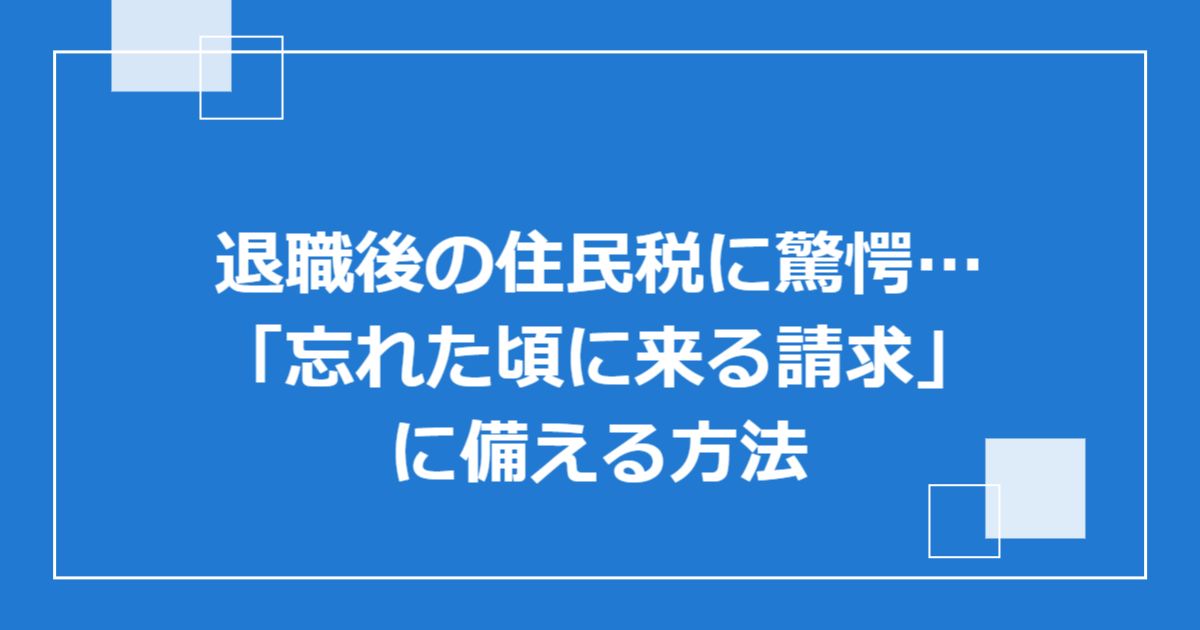
ハラスメントが原因で会社を辞め、
心身ともにようやく一息ついた数ヶ月後…。
市役所から届いた一通の封筒。開けてみると、数万円、人によっては十数万円にもなる「住民税」の納付書が入っていて、血の気が引いた…。
そんな経験はありませんか。
「もう会社から給料はもらっていないのに、なぜこんなに高額な請求が来るの?」
「今の収入じゃ、とても払えそうにない…」
この「忘れた頃に来る請求」は、多くの退職者が直面する大きな金銭的ストレスです。
しかし、仕組みを正しく理解し、万が一の時の対処法を知っておけば、必要以上に恐れることはありません。
この記事では、なぜ退職後に住民税の請求が来るのか、その仕組みと、もし支払いが困難な場合にどうすればよいのか、具体的な対処法を解説していきます。
なぜ今?「忘れた頃に来る」住民税の仕組み
退職後に届く住民税の請求書に多くの人が驚く最大の理由は、住民税が「前年1年間(1月1日~12月31日)の所得」に対して課税される、後払いの税金だからです。
会社員時代と退職後で「払い方」が変わる
まず、この仕組みを理解するために、2つの支払い方法の違いを知っておきましょう。
- 特別徴収
⇒ 会社員時代の払い方。会社が1年分の住民税を12分割し、毎月の給与から天引きして、あなたの代わりに納付してくれます - 普通徴収
⇒ 退職後の払い方。給与天引きができなくなるため、市区町村から送られてくる納付書を使って、自分で直接税金を納めます
退職すると、この「特別徴収」がストップします。そのため、
「収入があった昨年の所得」
にかかる税金を、
「収入が減った(または無くなった)今年」
に支払う、という時間差が生じます。
🔑 ワンポイント
いつ退職したかによって、その後の支払い方が変わるため、次の章で詳しく見ていきましょう
【退職時期別】いつ、どうやって支払う?
住民税の支払方法は、あなたが会社を辞めた時期によって大きく2つのパターンに分かれます。
パターン①:6月1日~12月31日に退職した場合
この場合、退職した月の翌月以降、その年度の5月までに支払うべき住民税の残額について、「普通徴収」に切り替わります。
後日、自宅に残額分の納付書が届く
退職後しばらくすると、お住まいの市区町村から、まだ支払いが済んでいない数ヶ月分の住民税の納付書が郵送されてきます。
基本的には、この納付書を使ってご自身で支払うことになります。
パターン②:1月1日~5月31日に退職した場合
この場合は少し特別で、その年度の5月までの住民税の残額が、退職時の最後の給与や退職金から一括で天引き(一括徴収)されるのが原則です。
最後の給与の手取りが少なくなるので注意
最後の給与から数ヶ月分の住民税がまとめて差し引かれるため、
「手取り額が思ったよりずっと少ない」
ということが起こりがちです。事前に心の準備をしておきましょう。
🌈 ちょっと一息
どちらのパターンでも、収入のあった前年1年分の住民税は、翌年6月頃に改めて納付書が届き、自分で支払う必要があります
もし払えなかったら…?絶対にやるべきことと相談窓口
この記事で最もお伝えしたい大切なポイントです。もし、手元の資金ではどうしても支払いが困難な場合、どうすればいいのでしょうか。
「無視」だけは絶対にダメ!
まず、大前提として
「納付書を無視する」
「支払いを放置する」
ということだけは、絶対に避けてください。支払いが遅れると、まず「督促状」が届き、法律に基づいた延滞金が加算されていきます。
それでも支払わずに放置すると、最終的には銀行口座や給与(新しい就職先が決まった場合)といった財産の差し押さえという、強制的な措置が取られてしまう可能性があります。
すぐに「市役所の担当窓口」へ相談を
「払えないかもしれない」と思った時点で、納税通知書に記載されている市区町村の役所の担当窓口(税務課、納税課など)に、必ず自分から電話・訪問して相談してください。
🔑 ワンポイント
「払う意思はあるが、現状では困難である」ということを正直に伝えることが何よりも重要です
役所の担当者は、あなたの状況をヒアリングした上で、以下のような公的な救済策を一緒に考えてくれます。
相談できること①:分割納付(分納)
年4回の分割でも支払いが難しい場合、さらに細かく月々での分割払い(分納)に応じてもらえる可能性があります。
「毎月〇円までなら支払えます」
という形で、あなたの収入状況に合わせた無理のない支払い計画を相談しましょう。
相談できること②:減免・猶予制度の申請
失業や病気など、特別な事情によって収入が著しく減少し、納税が困難になった人のために、多くの自治体では住民税を減額・免除したり、支払いを一定期間待ってくれたりする「減免・猶予制度」を設けています。
適用には所得などの条件があり、申請期限(多くの場合は納付期限まで)も決まっていますが、対象となる可能性があれば、申請方法などを詳しく教えてくれます。
まとめ
今回は、多くの退職者が頭を悩ませる「住民税」の仕組みと対処法について解説しました。
- 住民税は「前年の所得」にかかる後払いの税金である
- 退職時期(1-5月か6-12月か)によって、直後の支払い方が変わる
- 支払いが困難な場合、絶対に無視せず、すぐに役所の窓口に相談することが最重要
ハラスメントからの退職で心身ともに疲弊している中で、高額な請求書が届くと、絶望的な気持ちになってしまうかもしれません。 しかし、仕組みを知り、相談先を知っておけば、不意の請求に過度に怯える必要はありません。
公的な制度は、本当に困っている人を支えるために存在します。どうか一人で抱え込まず、専門の窓口を頼ってみてください。あなたの着実な生活再建を、社会も応援してくれるはずです。
→ 関連ページ:『休職・退職時に使える、あなたの権利「公的支援」完全ガイド』へ
→ 関連ブログ:『ハラスメントで退職。失業保険で損しないための知識』へ