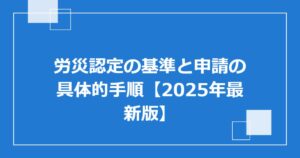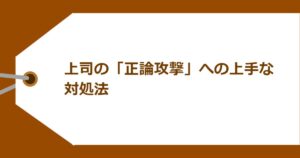就活セクハラ対策義務化へ【2025年法改正議論が本格化】
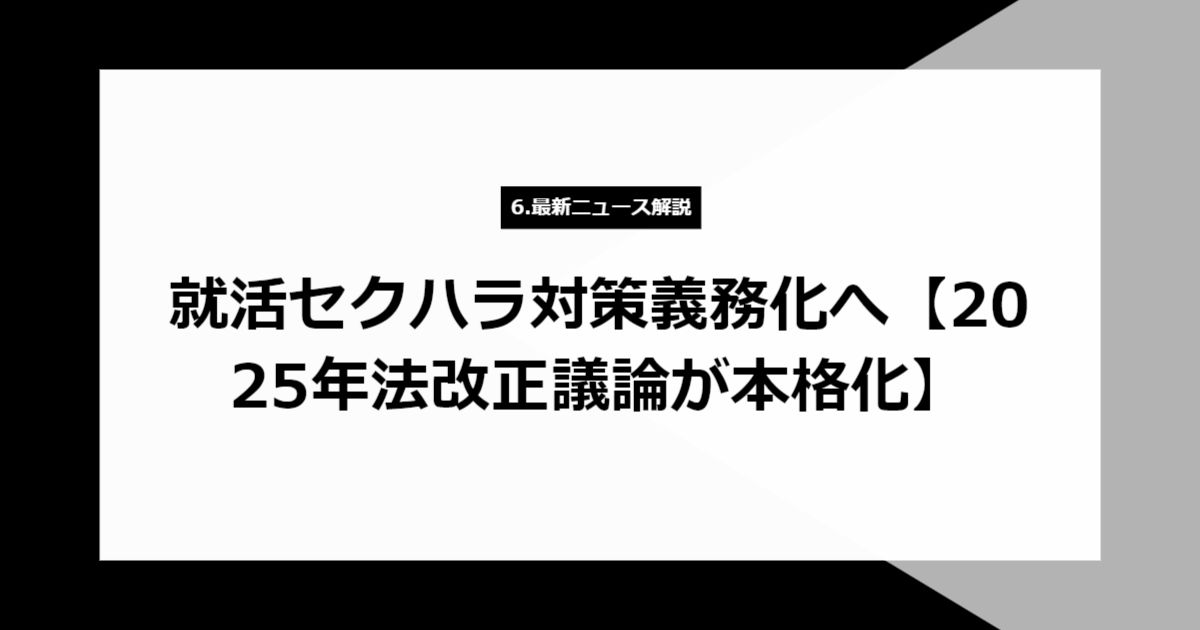
2024年10月22日、厚生労働省が
就活生へのハラスメント対策強化の一環として、企業への防止措置義務化に向けた検討を開始したと発表しました。
現在は「実施するのが望ましい」とされる努力義務に留まっている就活セクハラ対策が、ついに法的義務となる可能性が高まっています。
厚生労働省の調査によると、就職活動中の学生の約3分の1が被害を経験しているという深刻な現実があります。あなたの会社では、この変化への準備はもう始めていますか?
法改正に向けた動きが加速
厚生労働省は2024年内に議論をまとめ、2025年の通常国会において関連法案の提出を目指しています。つまり、早ければ2026年にも義務化が実現する可能性があるということなんです。
現在の法的位置づけと課題
職場におけるパワハラやセクハラについては、2020年に防止措置の企業義務化が実現しました。しかし就活生に対するハラスメントについては、これまで明確な法的保護がありませんでした。
🔑 ワンポイント
就活生は企業の労働者ではないため、労働法の保護対象から外れているのが現状です
厚労省の指針では「事業主は必要な注意を払うよう努めることが望ましい」とされているものの、法律上の防止義務ではないんです。立場の弱い学生を守る法的枠組みづくりが、いよいよ本格化してきました。
義務化が検討される背景
厚生労働省が過去2回行った調査によると、およそ回答者の3人に1人が就職活動中にセクハラを受けていることが判明しています。しかも、男女別で見ると意外にも男性の被害率が女性を上回っているという結果も出ています。
特に問題となっているのは次のような場面です。
- リクルーターとの面談時
⇒ 被害を受けた場面として最も多い(32.8%) - OB・OG訪問
⇒ 行為者として最も多い(38.3%) - インターンシップ中
⇒ 参加者の30.1%が被害を経験
インターンシップ長期化も影響
近年、インターンシップを重視する企業が増え、参加者の増加や期間の長期化が進んでいます。企業によっては、OB・OG訪問やリクルーターによる採用活動を通じて学生と接する機会が大幅に増えており、これが被害のリスクを高める要因の一つとなっているようです。
雇用関係のない相手への対策の難しさ
加害者と被害者の双方が企業と雇用関係にある職場ハラスメントと違い、被害者が雇用関係にない就活生へのハラスメントについては、労働施策総合推進法の定義のみでは対処できない側面があります。
就活生への対策について、職場における雇用管理の枠組みを広げて対処することができるかが、今後の重要な争点となっています。
企業に求められる対応
法改正を待たずとも、企業には就活生へのハラスメント対策が強く求められている状況です。
今から始められる対策
🌈 ちょっと一息
法改正前でも、積極的な対策は企業評価の向上につながります
厚生労働省が公開する「就活ハラスメント防止対策企業事例集」では、先進企業の取り組みが紹介されています。主なポイントは次の通りです。
方針の明確化と周知徹底
- トップメッセージによる禁止方針の明確化
- 採用担当者への研修実施
- 行為者への懲戒処分等の社内規定整備
相談体制の構築
- 就活生専用の相談窓口設置
- 相談窓口の積極的な周知
- 被害発覚時の迅速な対応体制構築
採用プロセスの透明性確保
- 学生との面談時のルール策定
- 複数名での対応を原則とする
- 応募者の個人情報保護の徹底
企業が負うリスク
就活セクハラが発生した場合、企業は深刻なリスクを負うことになります。
- 社会的信用の失墜
⇒ 報道やSNSで拡散される可能性 - 優秀な人材の獲得困難
⇒ 学生からの応募が激減する恐れ - 既存従業員への悪影響
⇒ 働く意欲やモラルの低下
人手不足が深刻な中、人材の確保は企業経営における最重要課題の一つです。就活セクハラの発覚で自社への入社を敬遠されるリスクは、計り知れないものがあります。
まとめ
就活セクハラ対策の義務化に向けた議論が本格化している今、企業は待ちの姿勢ではなく、積極的な対策が求められています。法改正を待たずに前倒しで対応することで、リスクを回避し、企業価値を高めることができるはずです。
学生も企業の姿勢をしっかりと見ています。安全で公正な採用活動を実現することは、優秀な人材を確保し、持続可能な企業成長につながる重要な投資と考えるべきでしょう。
今後の法改正の動向を注視しながら、できることから着実に対策を進めていくことが大切です。厚生労働省からの具体的な指針や企業事例集も参考に、自社に最適な防止策を検討してみてください。
→ 関連ブログ:『会社の相談窓口が頼りにならない時、どうすればいい?』へ
→ 関連ブログ:『ハラスメント被害を、家族や友人に話してもいい?』へ