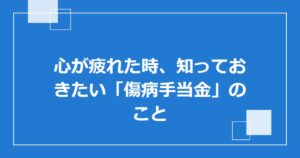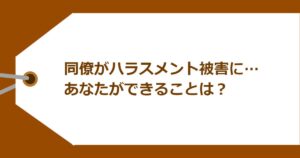「自爆営業はパワハラです」厚労省の“お墨付き”とその意味
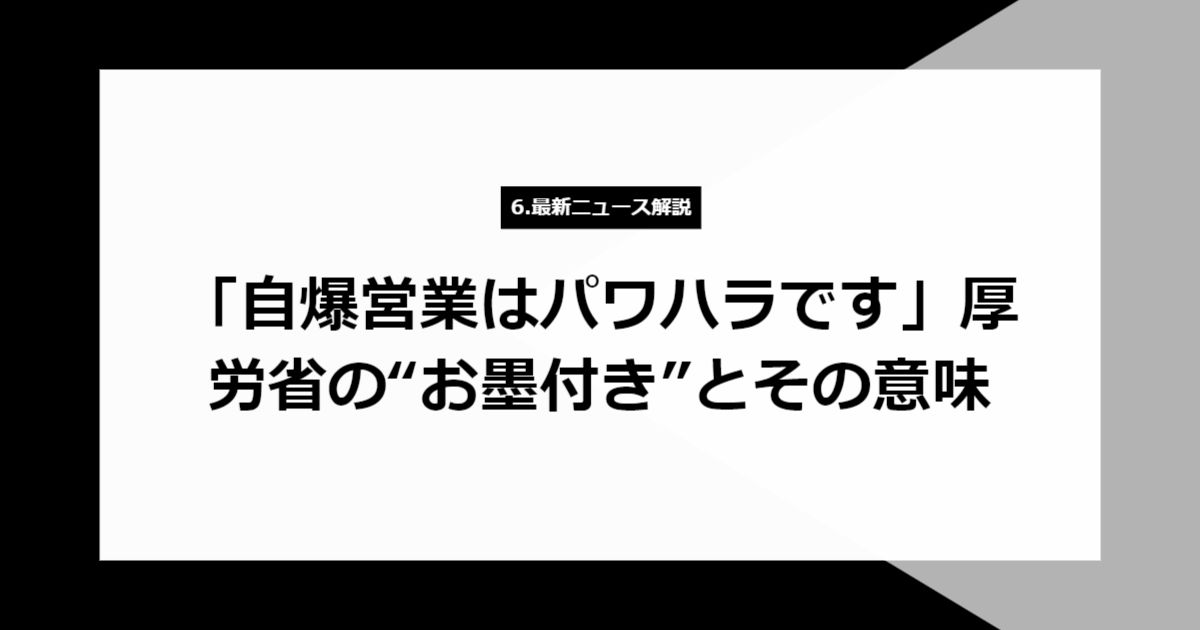
「自爆営業」がパワーハラスメントに該当しうる、
と厚生労働省が明確に示していることをご存知でしたか。
「当たり前」
「仕方ない」
と見過ごされてきたこの問題ですが、法律上はっきりと「NO」が突きつけられています。
今回は、多くの職場に根付くこの深刻な問題について、改めてその内容と意味を考えていきたいと思います。
「自爆営業」は、こんなに身近な問題
「自爆営業」と聞くと、特定業種の特別な話のように感じるかもしれません。しかし実際は、私たちの身近な職場で広く行われています。
こんなケース、あなたの周りにもありませんか?
- 保険会社⇒ 営業成績のために、自分や家族の保険に加入するよう言われる
- 自動車販売店⇒ 売れない車の値引き分を、営業担当者が自分で負担させられる
- 農協⇒ 割り当てられた共済の掛け金を、職員が自腹で支払う
- 飲食店⇒ 注文ミスや会計ミスの不足分を、従業員の給料から天引きされる
なぜ、これがパワハラになるのか?
この問題は以前から存在していましたが、法的な規制が曖昧だったため、多くの企業で慣習として見過ごされてきました。
厚労省が示す、明確な判断基準
パワハラ防止法では、以下の3つの要件を全て満たすものをパワハラと定義しており、「自爆営業」の強要はこれに該当する、と国が明確に判断したのです。
- 優越的な関係を背景とした言動 であり
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの であり
- 労働者の就業環境が害される もの
見過ごせない深刻な影響
実際に、ノルマのプレッシャーと経済的な負担という二重の苦しみから、心を病み、最悪の場合、自殺に追い込まれる方もいます。これは、決して他人事ではないのです。
「うちの会社では普通」の危険性
「みんながやっているから」
「昔からそうだから」
という感覚は、とても危険なサインかもしれません。
その「普通」、実はあなたの権利を侵害しています
そう感じてしまうこと自体が、問題の根深さを示しているのではないでしょうか。本来であれば主張できるはずのあなたの正当な権利が、「普通」という言葉のもとで侵害されている。今回の国の判断は、その異常な状況に「待った」をかけるものです。
🔑 ワンポイント
パワハラの3要件を満たす場合、自爆営業の強要は、個人の感覚ではなく、法律に基づいて明確にパワハラと判断されます
まとめ
今回の厚生労働省による指針の明記は、これまで「グレーゾーン」とされてきた行為に、社会として、そして法律として、明確な基準を示したという点で画期的な出来事です。
もしあなたが今、職場で理不尽な要求を受けていると感じているなら、それは「仕方ないこと」ではありません。法律も社会も、少しずつですが、確実に働くあなたの味方になってきています。一人で抱え込まず、まずは信頼できる相談先にその状況を話してみませんか。
どこに相談すればいいか分からず困っている方は、こちらのページで具体的な相談先を確認してみてください。
→ 関連ページ:『もう迷わない。目的別の最適な相談先マップ』へ