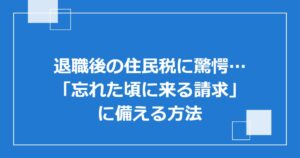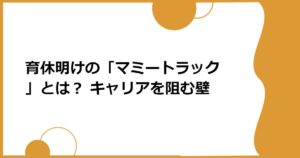リモートから「原則出社」へ。 その命令、ハラスメント?
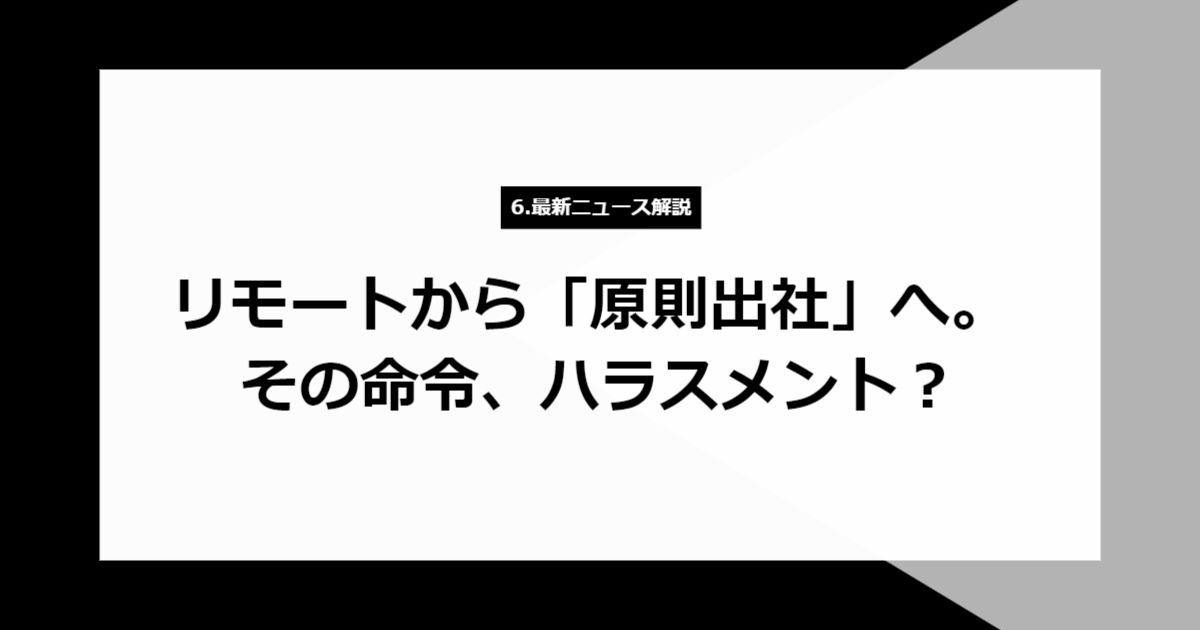
コロナ禍で一気に普及したリモートワーク。
しかし2025年後半、業績回復やコミュニケーション活性化を理由に、「原則出社」へと方針を転換する企業が急増しています。
「やっと育児と両立できる働き方を見つけたのに…」
「何の相談もなく、一方的に勤務地を変えるのはパワハラではないか?」
そんな悲鳴にも似た声が、今、多くの働く人たちから上がっています。
この記事では、実際の裁判例を基に、企業の「出社命令」はどこまで法的に認められるのか、そして、その命令がハラスメントになり得るのか、その境界線について専門家の視点を交えながら分かりやすく解説します。
なぜ企業は「原則出社」に戻したいのか?
従業員にとっては通勤時間の削減やワークライフバランスの向上など、多くのメリットがあったリモートワーク。なぜ今、企業は出社へと回帰しようとしているのでしょうか。
企業側が主張する「出社のメリット」
企業が「原則出社」を推進する背景には、主に以下のような理由があります。
- 偶発的なコミュニケーションの創出
⇒ 雑談や廊下での立ち話から、新しいアイデアやイノベーションが生まれるという期待 - 組織文化の醸成とチームの一体感
⇒ フェイス・トゥ・フェイスでの交流を通じて、企業理念の浸透や帰属意識の向上を図る - 新人・若手従業員の育成
⇒ OJT(On-the-Job Training)において、先輩の働き方を直接見て学ぶ機会を提供 - 情報セキュリティの確保
⇒ 社内ネットワークで業務を行うことによる、情報漏洩リスクの低減
これらの主張にも一理ありますが、従業員側が感じているリモートワークの恩恵との間には、深い溝があるのが現状です。
【判例解説】出社命令が「違法・無効」と判断された事例
大前提として、雇用契約書に勤務地の定めがなければ、企業は広範な「業務命令権」を持っており、出社命令は基本的には有効です。
しかし、その権利も無制限ではありません。ここで、リモートワーカーへの出社命令を「無効」と判断した重要な裁判例
「アイ・ディ・エイチ事件(東京地裁・令和4年11月16日判決)」
を見ていきましょう。
この事件で、会社側は「管理監督の観点からリモートワークを禁止する」として出社を命じましたが、裁判所は
「業務上の必要性がない」
として、その命令を権利の濫用であり無効だと判断しました。 この判例から、出社命令が違法と判断されうる具体的なケースを読み解くことができます。
ケース1:採用時に「在宅勤務」の合意があった
まず、採用時の雇用契約書に
「勤務場所は自宅とする」
といった記載がある、あるいは求人票に「フルリモート勤務」と明記され、その条件で合意して入社した場合です。この合意を一方的に覆す出社命令は、契約違反として無効と判断される可能性が非常に高いです。
ケース2:従業員の不利益が「通常甘受すべき程度」を著しく超える
出社することによって、従業員が被る生活上の不利益が、社会通念上、受け入れるべき範囲を著しく超える場合です。
- 育児・介護など、家庭生活上の深刻な不利益
⇒ 家族の介護や育児が困難になるなど、生活が成り立たなくなるほどの深刻な不利益が生じる場合 - 遠隔地への転居を会社が黙認していた
⇒ リモートワークを前提に、会社側の許可や黙認のもとで遠隔地に転居した従業員に対し、突然出社を命じる場合
こうした従業員側の事情を全く考慮しない命令は、権利の濫用と評価される可能性があります。
ケース3:出社命令に「業務上の必要性」が乏しい
先の「アイ・ディ・エイチ事件」で最も重視されたポイントです。
これまでリモートワークで全く問題なく業務を遂行し、高い成果を上げてきた従業員に対し、企業側が
「なぜ出社が必要なのか」
を合理的に説明できない場合、その命令は正当性を欠くと判断されます。
🔑 ワンポイント
特に、命令の裏に「あいつが気に入らない」といった嫌がらせなどの不当な動機が認められる場合は、パワハラとして違法性が問われます
出社命令に納得できない場合、私たちが取るべき行動
「自分のケースは、もしかしたら権利の濫用かもしれない」
そう感じた時に、感情的に反発するのではなく、冷静に取るべき行動をご紹介します。
まずは「契約書」と「就業規則」を確認
あなたの雇用契約書や会社の就業規則に、勤務場所についてどのような記載があるかを確認しましょう。
「勤務地は本社とする」
「会社は従業員の勤務場所を変更することができる」
といった記載があれば、会社の命令権が強い根拠となります。
「なぜ出社が困難なのか」を具体的に説明し、記録する
育児や介護、自身の健康上の問題など、出社が困難な理由を具体的に、かつ客観的な資料(診断書など)を添えて会社に説明し、代替案(週数日の出社など)を提案してみましょう。
その際のやり取りは、必ずメールなど記録に残る形で行うことが重要です。これは、後の交渉や法的手続きで「きちんと相談した」という証拠になります。
外部の専門家に相談する
当事者同士での話し合いが平行線に終わった場合は、一人で抱え込まず、外部の専門家を頼りましょう。
- 労働組合
⇒ 会社の組合や、個人で加入できるユニオンに相談し、団体交渉を申し入れる - 弁護士
⇒ 労働問題に詳しい弁護士に相談し、法的な観点から出社命令の有効性を判断してもらい、代理人として交渉を依頼する
🌈 ちょっと一息
特に「嫌がらせ」目的の出社命令など、ハラスメントの疑いが強い場合は、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします
まとめ
今回は、リモートワークから「原則出社」への移行をめぐる問題について、「アイ・ディ・エイチ事件」という実際の判例を基に解説しました。
- 企業の「出社命令」は基本的には有効だが、無制限ではない
- 「業務上の必要性」や「従業員の不利益の大きさ」が判断の分かれ目となる
- 納得できない場合は、まず契約書を確認し、会社と冷静に交渉することが重要
リモートワークという新しい働き方をめぐるルールは、まさに今、社会全体で一つひとつの事例を積み重ねながら形成されている最中です。 企業の業務命令権は尊重されるべきですが、それは従業員の生活や健康を犠牲にしてまで行使されるものではありません。
もしあなたが一方的な出社命令に悩んでいるのなら、まずは自身の権利を正しく理解し、冷静な対話の姿勢で会社と向き合ってみてください。
→ 関連ページ:『法律という名の盾。あなたを守る法律の限界と可能性』へ
→ 関連ブログ:『会社の相談窓口が頼りにならない時、どうすればいい?』へ