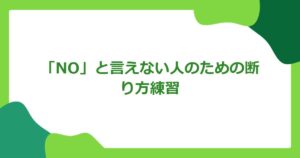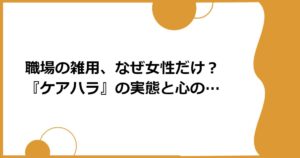東京都カスハラ防止条例施行 企業対応の実態
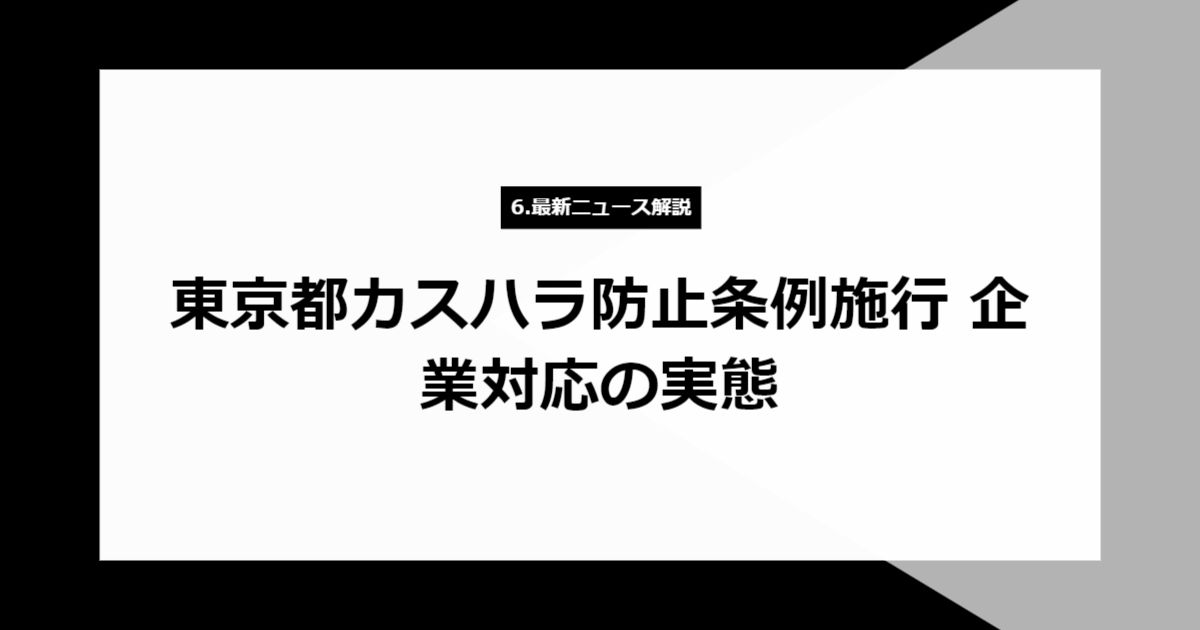
2024年10月1日、全国初となる
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行されました。
顧客からの理不尽な要求や暴言に悩む働く人たちにとって、大きな前進となるこの条例。しかし、企業の準備は果たして整っているのでしょうか。
実は、条例施行から約10ヶ月が経った今も、7割以上の企業が具体的な対策を講じていないという驚くべき実態が明らかになっています。一方で、積極的に取り組む企業との間には、大きな格差が生まれているのが現状です。
この記事では、東京都カスハラ防止条例の具体的な内容と、企業の対応実態について詳しく見ていきます。
全国初の条例が掲げる3つの柱とは
東京都カスハラ防止条例は、これまでにない画期的な内容を持つ条例です。
2024年4月に成立し、2024年10月1日から施行されたこの条例には、大きく分けて3つの柱があります。
- カスハラの一律禁止
⇒ 何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならないと明確に規定。これにより、カスハラが違法行為であることが条例上で初めて明文化されました。 - 各主体の責務を明確化
⇒ 東京都、顧客、就業者、事業者それぞれに、カスハラ防止のための積極的な取り組みを求めています。単に禁止するだけでなく、みんなで防止に努める姿勢を示しているんです。 - 具体的な指針と支援策
⇒ 2024年12月には詳細なガイドラインも策定され、企業が取るべき具体的な対策が示されました。東京都も研修支援などの施策を推進しています。
特に注目すべきは、罰則規定がないにも関わらず、カスハラを「違法」と明記した点です。これにより、社会全体でカスハラを許さない意識の醸成が期待されています。
条例の対象は業種を問わず東京都内で働くすべての人。サービス業だけでなく、医療・介護・製造業など、あらゆる分野が対象となっています。
企業対応に見える深刻な二極化
しかし、条例施行後の企業の対応実態を調べてみると、深刻な二極化が浮き彫りになりました。
株式会社エス・ピー・ネットワークの2025年8月調査では、「カスハラ対応を含む研修やマニュアル策定は半数以上が未対応」という結果が出ています。
さらに東京商工リサーチの調査では、対策を講じていない企業が7割超に達することが判明しました。
積極的企業の取り組み例
対応を進めている企業では、以下のような取り組みが行われています。
- 基本方針の策定・周知
⇒ カスハラを許さない企業姿勢の明文化 - 対応マニュアルの整備
⇒ 具体的な事例と対処法の文書化 - 専用相談窓口の設置
⇒ 被害を受けた従業員のケア体制構築 - 管理職向け研修の実施
⇒ 現場対応力の向上 - 録音・記録システムの導入
⇒ 証拠収集体制の整備
対応が遅れる企業の課題
一方、対策が進まない企業には共通の課題があります
- 人材不足
⇒ マニュアル作成や研修実施の人手が足りない - 資金面の制約
⇒ システム導入や研修費用の負担が重い - 認識不足
⇒ 法制化への危機感が薄い - ノウハウ不足
⇒ 何から始めればよいかわからない
特に中小企業では対応の遅れが顕著で、大企業との格差が拡大している状況です。
被害は深刻化、国レベルの法制化も進行
条例施行後も、カスハラ被害の実態は依然として深刻です。
同調査では
「約7割が消費者から、約5割が取引先からのカスハラ経験あり」
という結果が示されており、宿泊業や飲食店での被害が特に多いことがわかっています。
さらに深刻なのは、
「カスハラ被害で従業員の休職・退職が13.5%の企業で発生」
している点です。これは企業にとって人材確保の観点からも重大な問題となっています。
国レベルでの動きも加速
東京都の取り組みと並行して、国レベルでの法制化も急速に進んでいます。
厚生労働省は2025年の通常国会において、カスハラ対策を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正案を提出する方針を示しています。これにより、2026年度には全国の企業にカスハラ対策が法的義務となる見通しです。
また、三重県、埼玉県、北海道でも同様の条例制定に向けた検討が始まっており、自治体レベルでの取り組みが全国に拡大しています。
🔑 ワンポイント
法制化の流れは止まりません。企業の対応は「任意」から「義務」への転換点を迎えています
パーソル総合研究所の調査では、「信頼資産」が高い職場ほどカスハラ被害の負の影響が軽減されることも判明しており、日頃からの職場環境づくりの重要性が浮き彫りになっています。
まとめ
東京都カスハラ防止条例の施行により、カスハラ対策は新たな局面を迎えました。しかし、企業の対応実態には明確な二極化が見られ、7割以上の企業がまだ具体的な対策を講じていないという厳しい現実があります。
しかし、2026年度には国レベルでの法制化が見込まれており、企業にとってカスハラ対策は避けて通れない課題となりました。特に人手不足が深刻化する中、従業員を守り、働きやすい環境を整備することは、企業の持続的成長にとって不可欠な取り組みです。
まだ対策に着手していない企業は、今すぐにでも基本方針の策定から始めることをお勧めします。従業員が安心して働ける職場こそが、これからの時代に選ばれる企業の条件です。
→ 関連ブログ:『「お客様は神様」はもう古い?広がる"カスハラ"防止条例とは』
→ 関連ブログ:『カスハラ対策、義務化へ。職場はどう変わる?』へ