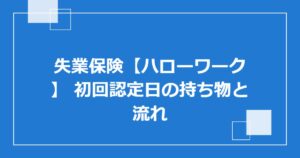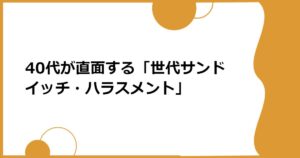カスハラ対策2026年施行 取引先からのハラスメントも義務化
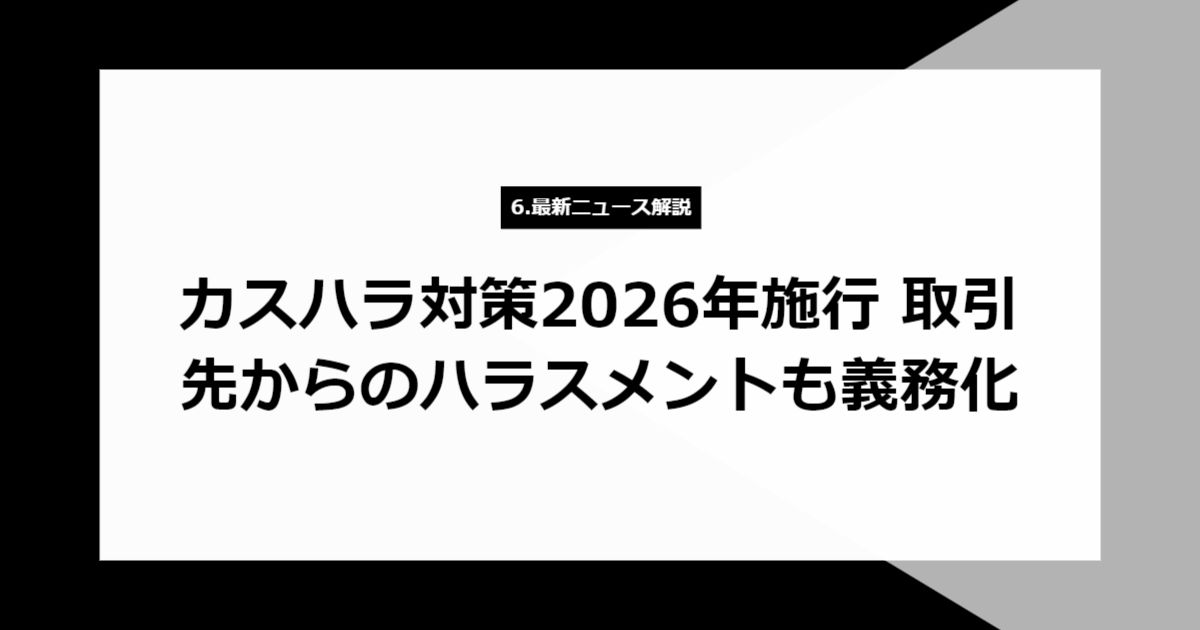
顧客からの理不尽な要求
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」
が深刻な社会問題となる中、2025年6月、ついにカスハラ対策を企業に義務付ける法改正が成立しました。
この法改正で注目すべきは、一般消費者からのハラスメントだけでなく、取引先企業からのハラスメントも対象に含まれるという点です。
「発注元」という優越的な立場を利用した無理な要求や人格否定の暴言に、多くの従業員が心を病んでいます。2026年中の施行を前に、企業は今から準備を始める必要があります。
この記事では、成立した法改正の内容と、企業間取引におけるハラスメントがどのように扱われるのかを、分かりやすく解説します。
【本記事について】
この記事は2025年10月2日時点での公開情報に基づいています。法改正は2025年6月に成立済みですが、具体的な対応措置の詳細を定める厚生労働省の指針は今後策定予定です。最新の情報は厚生労働省の公式サイト等でご確認ください。
なぜ今「カスハラ対策」が法律で義務化されたのか
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などからの著しい迷惑行為のことです。
深刻化する被害の実態
接客業や営業職を中心に、カスハラによる被害が深刻化しています。理不尽な要求、長時間の叱責、土下座の強要、SNSでの晒し行為など、その内容は多岐にわたります。
こうした行為は、被害に遭った従業員のメンタルヘルスを深刻に害し、休職や離職の直接的な原因となっています。
カスハラを経験した人の多くが、強いストレスや自己肯定感の低下を感じていることが各種調査で報告されており、もはや個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題となっているんです。
これまでの対策は「努力義務」だった
現在のパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)では、自社の従業員同士のハラスメント対策(相談窓口の設置など)は、企業の規模を問わず「義務化」されています。
しかし、顧客や取引先など社外からのハラスメントについては、これまで企業の「努力義務」に留まっていました。つまり、「対策を取ることが望ましい」という弱い規制しかなかったんです。
この「努力義務」という位置づけが、結果として対策が進まない大きな要因となり、多くの被害者を生み出してしまっていました。
🔑 ワンポイント
自社の従業員を守るためには、社内だけでなく「社外からのハラスメント」にも目を向ける必要がある。それが社会の共通認識となり、法改正へとつながりました
【2025年6月成立】カスハラ対策義務化の法改正、3つのポイント
こうした状況を打開するため、2025年6月4日、カスハラ対策を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法が参議院本会議で可決・成立しました。
2026年中(早ければ2026年10月頃)の施行が予定されています。
①カスハラの定義が法律で明確化される
今回の法改正では、カスハラが以下の3つの要素を満たすものと定義されました。
カスハラの3要素
- 誰が行うか
⇒ 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者 - どんな行為か
⇒ 社会通念上相当な範囲を超えた言動 - どんな影響があるか
⇒ 労働者の就業環境が害される
重要なのは、「顧客」だけでなく「取引先」も明確に対象に含まれているという点です。
つまり、企業間取引(BtoB)における優越的地位を利用したハラスメントも、カスハラとして法的に規制されることになります。
②企業に具体的な対策措置が義務付けられる
企業は、カスハラ防止のための「雇用管理上の措置」を講じることが義務付けられます。
具体的な措置の内容は、今後厚生労働省が定める指針で示される予定ですが、以下のような対応が求められると考えられています。
企業に求められる主な措置(想定)
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- カスハラ案件の事後の迅速かつ適切な対応
- カスハラへの対応の実効性を確保するための抑止措置
これらは、既に義務化されているパワハラやセクハラの防止措置と同様の枠組みです。
③違反した場合の行政対応
企業が必要な措置を講じていない場合、行政による助言、指導、勧告を受ける可能性があります。さらに、勧告に従わない場合には、企業名が公表されることもあります。
🌈 ちょっと一息
法律での義務化により、企業は「顧客だから」「取引先だから仕方ない」という言い訳ができなくなります。従業員を守るための具体的な行動が求められます
取引先からのハラスメント、具体的にはどんな行為?
企業間取引における優越的地位を利用したハラスメントは、以下のような形で現れます。
よくある事例
- 契約外の業務の無償強要
⇒ 「発注してやってるんだ」という態度で、契約書に記載のない業務を無償で強要する - 過度な精神的攻撃
⇒ 仕様変更の責任を一方的に押し付け、長時間にわたって担当者を罵倒する - 実現不可能な要求
⇒ 「他社ならできる」と、明らかに実現不可能な短納期や品質基準を要求する - 個人への直接攻撃
⇒ 会社を通さず、担当者個人に「次回は必ず達成します」と確約を強要する
なぜ声を上げにくいのか
取引先からのハラスメントが特に深刻なのは、被害者が声を上げにくいという構造的な問題があるからです。
「取引を打ち切られるかもしれない」
という恐怖から、企業側も毅然とした対応を取りづらく、結果として従業員が我慢を強いられる状況が続いてきました。
しかし、今回の法改正により、企業は自社の従業員を守る法的義務を負うことになります。取引先との関係性に配慮しつつも、従業員の安全と健康を最優先に考えた対応が求められます。
まとめ
今回は、2025年6月に成立したカスハラ対策義務化の法改正と、取引先からのハラスメントも対象に含まれることについて解説しました。
この記事のポイント
- 2025年6月、カスハラ対策を企業に義務付ける法改正が成立した
- 取引先からのハラスメントも明確に義務化の対象に含まれている
- 2026年中の施行に向けて、企業は今から準備を始める必要がある
この法改正は、働くすべての人を理不尽なハラスメントから守るための、大きな一歩です。
企業は、取引先との関係性においても、自社の従業員の安全と健康を守る責任を明確に問われることになります。
施行までの間に、相談窓口の設置や対応方針の策定など、必要な準備を進めていくことが重要です。
一人の働く人間として、そして社会の一員として、この法改正がもたらす変化をしっかりと理解し、より良い職場環境の実現につなげていきましょう。
→ 関連ページ:『法律という名の盾。あなたを守る法律の限界と可能性』へ
→ 関連ブログ:『カスハラ対策、義務化へ。職場はどう変わる?』へ