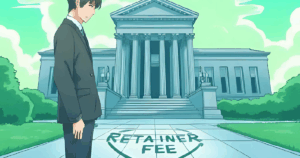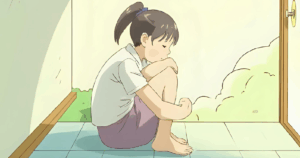2026年カスハラ法改正で「企業がすべきこと」

2026年中に、私たち働く人にとって
重要な法改正が施行される見込みです。
これは、顧客や取引先からの理不尽な要求、
いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)
への対策を、企業に雇用管理上の義務として課すものです。この改正は、一見すると
「会社が頑張る話」
のように聞こえます。しかし、もし企業が十分な対策をとらなければ、現場で働くあなた自身に心理的・物理的な負担が生じるリスクが高まる可能性があります。
「うちの会社は対策を進めているのかな?」
「もし会社が動いてくれなかったら?」
そんなふうに不安に感じているあなたのために、法改正の趣旨と指針に基づき、企業が講じることが強く求められる対策を解説していきます。
企業に義務付けられたカスハラ対策の「3つの柱」
改正後の労働施策総合推進法では、企業にカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置を講じる義務が課されます。
指針に基づき、企業が講じることが強く求められる対策として、主に以下の3点が中心になると見られています。
1. 相談体制の整備と周知徹底
企業は、カスハラに関する相談窓口を設置し、その窓口の担当者や対応手順を労働者全員に周知する必要があります。
具体的な対応
- 外部の専門機関を含めた相談窓口を設けること
- 相談があれば、プライバシーを守り、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 相談を理由に不利益な扱いをしない旨を明確に伝えること
2. 被害者への適切な配慮
カスハラが発生した場合、企業は被害を受けた労働者の心身の状態に応じた適切な配慮を行うことが求められます。具体的な措置の範囲は政令・指針で定められる見込みです。
具体的な対応
- 配置転換や休職などの措置を講じること
- 産業医やカウンセラーなどによる心のケアを受けられるようにすること
3. 再発防止とマニュアルの策定
単に問題を解決するだけでなく、カスハラ防止のための明確な方針策定や再発防止のための措置も重要です。
具体的な対応
- カスハラ防止のための明確な方針を策定し、労働者に周知・啓発すること
- 顧客や取引先に対して、ハラスメント行為をしないよう協力を求めること(毅然とした対応)
🔑 ワンポイント
今回の改正は、カスハラが「現場の負担」ではなく「企業の責任」であることを明確に示したものです
「取引先・顧客からのハラスメント」への具体的な対応手順
今回の法改正の重要なポイントの一つが、顧客や取引先(社外)からのハラスメントにも企業が対処する義務を負う点です。改正法では「顧客等からの言動」を含むハラスメントが対象となる規定を設ける方向です。
あなたの会社が取るべき手順を知っておけば、いざという時に「会社は何もしてくれない」という事態を避けることができます。
会社を動かすための3つの重要ポイント
- マニュアルと指針の作成・周知
- 会社が「カスハラは許さない」という明確な指針を策定し、それを顧客対応の最前線にいる社員に徹底することが求められます
- 毅然とした対応の導入
- 悪質なカスハラに対しては、サービス提供の拒否、取引停止、法的措置(警察への通報など)を含めた毅然とした態度を取るための基準を設ける必要があります
- 会社が毅然とした対応を取ることで、現場の担当者であるあなたは、一人で抱え込まずに済みます
- 担当者の配置と支援
- カスハラ対応の専門チームや責任者を決め、対応を一元化することも重要です
- ハラスメントの加害者と直接対峙する現場担当者に対し、心理的なサポートや、交代要員を配置するなどの負担軽減策を講じることが求められます
🌈 ちょっと一息
法改正の目的は、働く人たちが安心して業務に取り組める職場環境を整備することです
あなたの会社は大丈夫?企業の対策レベルを見極める視点
法改正で義務化されても、
「とりあえず相談窓口だけ作った」
というように、形だけの対策に留まっている企業も少なくありません。
あなたの心と生活を守るため、ご自身の会社の対策レベルをチェックしてみましょう。
企業のカスハラ対策チェックリスト
以下の項目があなたの職場で明確になっているか確認してください。
- 相談窓口の担当者は、被害者への共感性と守秘義務について十分な研修を受けていますか?
- カスハラ対応マニュアルは、現場の誰もがアクセスでき、実際の事例に基づいた具体的な手順が書かれていますか?
- カスハラ発生時、被害者が別の業務やポジションへの配置換えを希望した場合、柔軟に対応できる体制がありますか?
- カスハラをされた際に、対応を拒否したり、上司に引き継いだりできる明確なルールがありますか?
もし、これらの対策が不十分だと感じた場合、あなたの会社はまだ法的な義務を果たしきれていない可能性があります。
対策が不十分な場合に利用できる社外の窓口
社内の相談窓口が機能していないと感じたときは、すぐに社外の専門機関を利用してください。
- 労働局の総合労働相談コーナー
⇒ 無料で相談でき、会社への指導や助言を行ってくれます - 弁護士
⇒ 会社への法的な責任追及や、具体的な対応策について専門的なアドバイスを受けられます
まとめ
2026年に施行が見込まれているカスハラ対策の義務化は、ハラスメントに苦しむ労働者を守るための大きな一歩です。
企業は、指針に基づき相談体制の整備、被害者への配慮、そして再発防止策を講じることが強く求められます。特に、取引先や顧客からのハラスメントに対しても、毅然とした対応を取ることが求められます。
あなたの会社が「形だけ」の対策に留まっていないかチェックし、もし不十分だと感じたら、労働局や弁護士など、法的な支援を受けられる外部機関を積極的に頼ってください。
法律は、あなたが安心して働ける職場環境を守るための強い味方です。
→ 関連ページ:『なぜ人はハラスメントをしてしまうのか』へ
→ 関連ブログ:『会社の相談窓口が頼りにならない時、どうすればいい?』へ