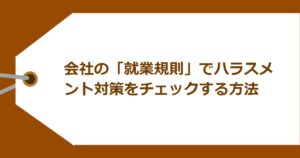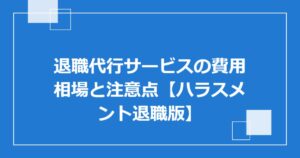「ジェンハラ」に高まる関心! 新ハラスメントの実態
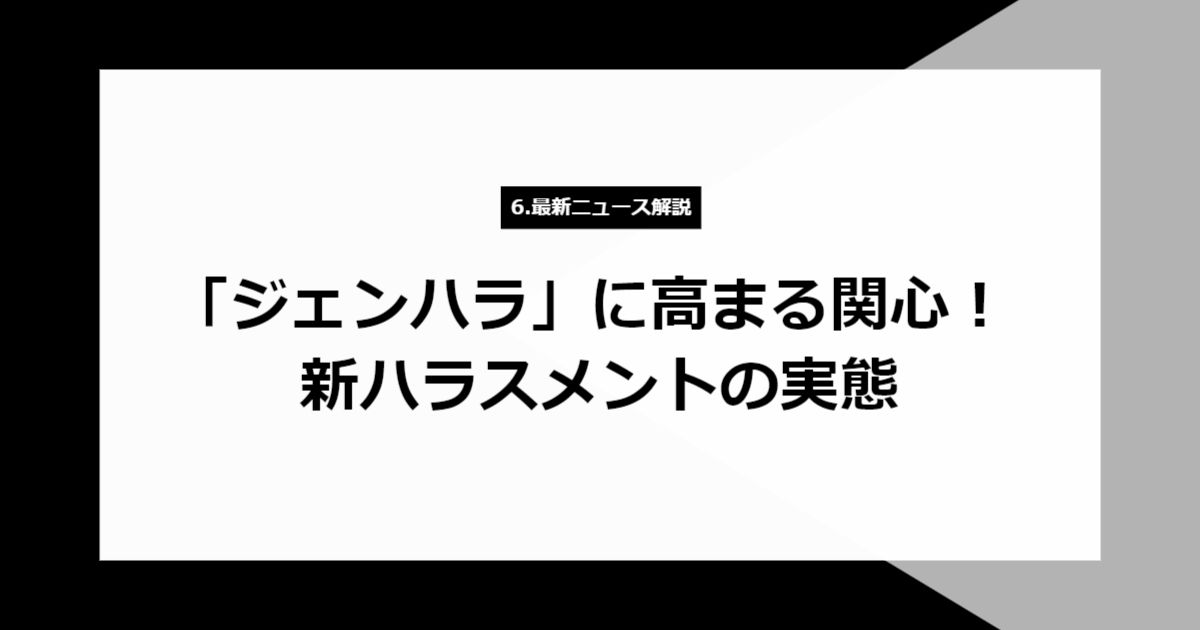
近年、職場で新たに注目されている
ハラスメントがあります。
それが「ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)」です。
日本労働組合総連合会(連合)が2024年6月に発表した調査では、多くの働く人が職場でジェンダーに関する固定観念に基づくいやがらせを経験している実態が明らかになり、改めて注目が集まっています。
従来のセクシュアルハラスメントとは異なり、性別に基づく固定観念や偏見によって相手を不快にさせる言動を指します。
「女性だから細かい作業が得意でしょ」
「男性なら重いものを持って当然」
といった、一見悪意のない発言も、実はジェンハラに該当する可能性があるんです。
多様性への意識が高まる中、企業の人事担当者や管理職の間で、このジェンハラ対策が急務となっています。なぜ今、ジェンハラが注目されているのでしょうか。詳しく解説します。
ジェンダーハラスメントとは?セクハラとの違いを理解する
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは、性別に基づく固定観念や偏見によって、相手に不快感や不利益を与える言動のことです。働き方の多様化とジェンダー平等への意識向上を背景に、その注目度は年々高まっています。
セクハラとジェンハラの決定的な違い
多くの人が混同しがちですが、セクシュアルハラスメントとジェンダーハラスメントには明確な違いがあります。
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- 性的な言動が中心
- 身体的接触や性的な冗談、画像の掲示など
- 明確に「性的」とわかる内容
- ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
- 性別役割の押し付けが中心
- 「男性らしさ」「女性らしさ」の強要
- 性別による能力や適性の決めつけ
- 一見「親切」や「配慮」に見える場合もある
近年ジェンハラが注目される理由
- 調査で可視化された実態
⇒ 連合の2024年の調査などで、職場でジェンダーに関する不適切な言動の被害が報告されている実態が数字で示されたことが、問題意識を高める大きなきっかけとなりました - Z世代の職場進出
⇒ ジェンダーフリーに対する意識が特に高いZ世代が職場の中核を担うようになり、従来「当たり前」とされてきた発言や慣習に対して疑問の声が上がるようになりました - 企業の多様性推進
⇒ ESG経営やダイバーシティ&インクルージョンの観点から、企業が積極的にジェンダー問題に取り組むようになり、これまで見過ごされてきた問題が表面化しています
🔑 ワンポイント
ジェンハラは「悪意がない」からこそ根深い問題。無意識の偏見に気づくことから対策が始まります
職場でよくあるジェンハラの具体例と問題点
実際の職場では、どのような言動がジェンハラに該当するのでしょうか。報告されている具体的な事例を通して見ていきましょう。
よくあるジェンハラの典型例
① 能力・適性の決めつけ
- 事例1:業務分担での偏見
- 「女性だから細かい作業をお願いします」
- 「男性なので力仕事は任せます」
- 何が問題なのか
⇒ 個人の能力や希望を無視して、性別だけで業務を振り分けることで、キャリア形成の機会を奪う可能性があります
② 家庭・プライベートへの干渉
- 事例2:結婚・出産に関する発言
- 「もう30歳だし、そろそろ結婚は?」
- 「男性なら家族を養わないと」
- 何が問題なのか
⇒ 個人のライフプランに性別による押し付けを行い、プライバシーを侵害しています
③ 外見・服装への過度な指摘
- 事例3:ジェンダー規範の押し付け
- 「女性らしくもっと明るい色を着たら?」
- 「男性なのにピンクのシャツは変」
- 何が問題なのか
⇒ 外見や振る舞いに性別による「らしさ」を強要し、個性や自己表現を制限しています
「善意」が生むジェンハラの危険性
特に注意が必要なのは、「親切心」や「配慮」のつもりで行われるジェンハラです。
- 配慮のつもりが差別に
- 「女性だから重いものは持たなくていいよ」
⇒ 本人が希望していない「配慮」は、能力を低く見られていると感じさせる - 「男性なんだから弱音を吐かずに頑張って」
⇒ 男性のメンタルヘルスを軽視し、相談しにくい環境を作る
- 「女性だから重いものは持たなくていいよ」
🌈 ちょっと一息
「女性だから」「男性だから」で始まる発言は、一度立ち止まって考えてみることが大切です
企業が取り組むべきジェンハラ対策と法的リスク
現在、多くの企業がジェンハラ対策に本格的に取り組み始めています。放置すれば深刻な法的リスクを招く可能性もあるため、組織的な対応が求められています。
企業に求められる具体的対策
- 研修・教育の充実
⇒ アンコンシャス・バイアス研修や、多様性を尊重する職場作りのための管理職向け研修 - 制度・環境の整備
⇒ 性別に関係なく能力で評価する人事制度の見直しや、ジェンハラ専門の相談窓口の設置 - 就業規則・ガイドラインの整備
⇒ ジェンハラの定義を明文化し、禁止される言動の例示や違反した場合の処分規定を設ける
法的リスクと企業責任
ジェンハラは、男女雇用機会均等法に基づく性別を理由とする差別や不利益な取扱いに該当する可能性があり、企業が対策を怠った場合は行政指導や民事上の責任につながる恐れがあります。
個人でできるジェンハラ対策と相談方法
企業の対策を待つだけでなく、私たち一人ひとりができることもあります。
ジェンハラ被害を受けた場合の対処法
- 記録を残す
⇒ 発言内容、日時、場所、周囲にいた人などを正確に記録しましょう - 信頼できる人に相談する
⇒ 社内のハラスメント相談窓口や労働組合、社外では労働局の総合労働相談コーナーや弁護士などが相談先になります
加害者にならないための予防策
- 言葉遣いを見直す
⇒ 「女性だから/男性だから〜」といった決めつけの表現を避け、個人の能力や経験に着目する - コミュニケーションの改善
⇒ 性別ではなく、その人の個性や希望を尊重し、多様な価値観があることを認識する
まとめ
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)は、職場で理解しておきたい重要なハラスメントです。2024年の連合の調査でも多くの被害が報告されているなど、決して他人事ではありません。
性別に基づく固定観念や偏見による言動が問題となり、企業には男女雇用機会均等法の観点からも対策が求められています。個人レベルでは、被害を受けた場合の記録と相談、そして加害者にならないための意識改革が大切です。
多様性を尊重し、性別にとらわれない職場作りは、すべての人が能力を発揮できる環境につながります。一人ひとりの意識改革から、より良い職場環境を築いていきましょう。
→ 関連ページ:『まず知るべき、パワハラの6つの顔(タイプ)』へ
→ 関連ブログ:『「SOGIハラ」って何?知らずに加害者になる前に』へ