フリーランス保護新法 「ハラスメント防止措置」の具体例
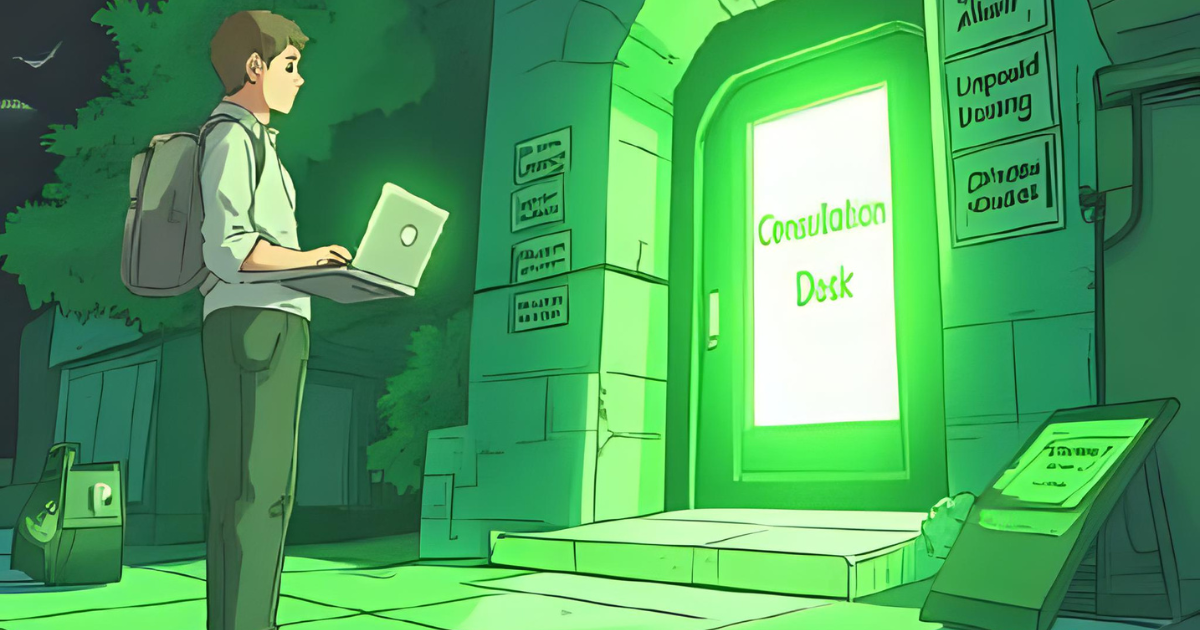
フリーランス保護新法が施行され
ついに発注事業者にハラスメント防止措置の義務が課されました。
これは、契約内容や報酬面で弱い立場になりがちなフリーランスを、
「優越的な立場を利用した不当な要求」や「パワハラ・セクハラ」といったハラスメントから守るための強力な盾となるものです。
この記事では、この防止措置がフリーランスにとって具体的に何を意味するのか、そして、発注事業者が現場で何をすべきかを解説します。法律の知識を武器に、あなたの権利と孤立を防ぐ方法を学びましょう。
義務の対象となる「ハラスメント」の範囲と具体例
フリーランス保護新法は、発注事業者に
「ハラスメント防止」
を義務付けていますが、このハラスメントの範囲は、一般的な職場内のパワハラ・セクハラにとどまりません。
発注事業者が優越的な立場を利用した不当な行為も含まれるのが大きな特徴です。
1. 契約上の優越的地位の濫用
発注事業者が立場を利用して行う、フリーランスの利益を不当に害する行為も、この防止措置の対象となり得ます。
- 業務の一方的な変更
⇒ 当初の契約にはなかった業務や、大幅な納期短縮を一方的に押し付ける - 無償での追加要求
⇒ 契約外の軽微でない修正や、追加作業を「サービス」として無償で要求する - 不当な報酬の減額
⇒ 成果物に問題がないにもかかわらず、一方的な理由をつけて報酬を減らしたり支払いを遅延したりする
2. 一般的なパワハラ・セクハラ行為
オフィス内やオンライン会議など、業務遂行中に発生する一般的なハラスメントも当然対象です。
- 精神的な攻撃
⇒ 発注元の担当者による威圧的な言動や、人格を否定する発言 - セクシャルハラスメント
⇒ 業務に関係のない性的な言動や、不必要なプライベートの詮索
🔑 ワンポイント
フリーランス保護新法の防止措置は、フリーランスの働き方を根本的に変える大きな一歩です
発注事業者が講じるべき具体的な「防止措置」とは?
法律の義務を果たし、フリーランスを守るため、発注事業者は具体的に以下の措置を講じることが求められます。
1. 方針の明確化と周知
ハラスメントに対する明確な方針を定め、それを関係者全員に周知徹底することが重要です。
- 禁止事項の明記
⇒ 優越的な立場を利用した不当な要求や、各種ハラスメントを禁止する旨を明確に定める - 研修の実施
⇒ 発注担当者である従業員に対し、ハラスメント防止やフリーランス保護新法の知識に関する研修を実施する
2. 相談窓口の設置と適切な運用
最も重要なのは、フリーランスが安心して利用できる相談窓口を設けることです。
- 窓口の設置
⇒ フリーランスからのハラスメント相談を受け付ける専用窓口を設置する - 適切な対処
⇒ 相談があった場合、迅速に事実確認を行い、被害者への配慮を含めた適切な措置を講じることが求められます
3. 再発防止策の実施
ハラスメントが発生した場合、原因を究明し、再発防止のための措置を講じる必要があります。
- 原因の特定
⇒ なぜハラスメントが起きたのか、組織的な背景を含めて調査する - 懲戒処分
⇒ ハラスメントを行った発注事業者の担当者に対し、厳正な処分を行う
🌈 ちょっと一息
ハラスメント防止措置は、会社内の従業員だけでなく、フリーランスにも公平に適用される必要があります
義務違反の事業者に「フリーランスが取るべき対抗策」
発注事業者がこれらのハラスメント防止措置を怠り、被害が発生した場合、フリーランスは泣き寝入りする必要はありません。法律によって、行政機関への申告という強力な対抗策が用意されています。
1. 行政機関への「申告」という武器
防止措置義務に違反した発注事業者は、指導や助言の対象となります。
- 公正取引委員会
⇒ 優越的地位の濫用にあたる不当な取引行為について申告できます - 中小企業庁
⇒ 取引上の問題について、指導や助言を求めることができます - 厚生労働省
⇒ 広範な労働環境の問題について相談できます
2. 権利を守るための「記録」の徹底
行政機関に申告する際も、具体的な証拠が不可欠です。
- 時系列での記録
⇒ ハラスメントや不当な要求があった日時、場所、内容を詳細に記録します - 客観的な証拠
⇒ メールやチャットのスクリーンショット、音声録音など、証拠能力の高いものを確保します
3. 弁護士等の専門家への相談
ハラスメントが原因で損害を被った場合、発注事業者を相手取った損害賠償請求を検討できます。
- 損害賠償請求
⇒ ハラスメントによって生じた精神的苦痛や経済的損失について、賠償を求めることが可能です
まとめ
この記事では、フリーランス保護新法により発注事業者に義務付けられたハラスメント防止措置の具体例について解説しました。
この記事のポイント
- ハラスメントの範囲には、一般的なパワハラ・セクハラに加え、優越的な立場を利用した不当な要求も含まれる
- 発注事業者は、フリーランスのための専用の相談窓口設置や研修の実施が求められる
- 義務違反の事業者に対し、フリーランスは公正取引委員会など行政機関に申告できるという強力な対抗策を持つ
新法は、フリーランスが不当な圧力に屈することなく、安心して働ける環境を築くための強力な後ろ盾です。法律の知識をあなたの武器にして、ご自身の権利を守るため積極的に活用しましょう。
→ 関連ページ:『法律という名の盾。あなたを守る法律の限界と可能性』へ
→ 関連ブログ:『施行から約11ヶ月 フリーランス保護新法 3つの重要ポイント』へ

