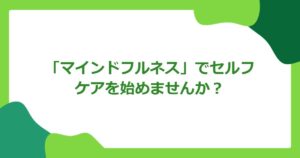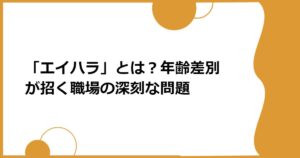「テクハラ」って何?デジタル格差が生む新しい職場の悩み
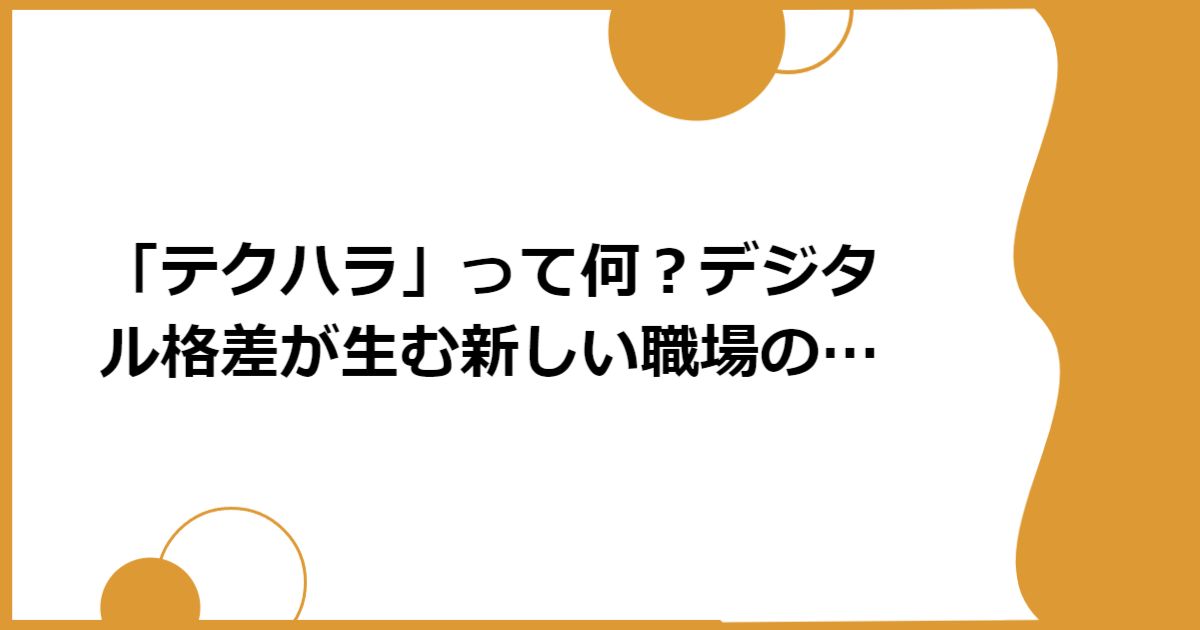
最近、あなたの職場で
「テクハラ」
という言葉を耳にしたことはありませんか?
正式には「テクノロジーハラスメント」と呼ばれるこの新しいハラスメントが、今、多くの職場で深刻な問題となっています。
「パソコンなんて簡単じゃないですか」
「こんなことも知らないんですか?」
そんな何気ない一言が、実は相手を深く傷つけているかもしれません。
デジタル化が急速に進む2025年、誰もが被害者にも加害者にもなりうるテクハラの実態を知っておくことは、もはや必須の知識といえるでしょう。
テクハラとは何か?従来のハラスメントとの違い
テクハラとは、ITの知識が乏しく、パソコンやスマートフォンなどのIT機器を苦手とする人へのいじめや嫌がらせを指します。
従来のパワハラが立場の優位性を利用したハラスメントであるのに対し、テクハラはデジタルネイティブと呼ばれる若年層からデジタル機器に弱い中高年層に行われることが特徴です。
つまり、部下から上司へも、あるいは同僚間でも起こる可能性があり、誰もが加害者・被害者になりやすいハラスメントなんです。
テクハラが注目される背景
2025年現在、テレワークの普及や業務のIT化により、これまでデジタル機器を使わずに仕事をしてきた人にとって、機器の操作は容易ではありません。
企業が急ピッチでデジタル化を進めた結果、IT環境への適応に時間を要する従業員への「テクハラ」が急増しているんです。
具体的な事例
- 「こんなこともできないのか」と心ない言葉を浴びせる
- わざと難解なIT専門用語を多用して説明する
- ITスキルを超えた高度な業務を強要する
- 「よく今までやってこれましたね」などと侮辱する
🔑 ワンポイント
従業員間のITリテラシーの差が、テクハラを引き起こす最大の原因。「これくらいできて当然」という思い込みが、相手を傷つけている
職場で実際に起きているテクハラの深刻な実態
テクハラは単なる「ちょっとした嫌がらせ」では済まされません。2025年のデジタル社会では、ITスキルの有無が業務効率に直結するため、被害者は深刻な精神的苦痛を受けることが多いんです。
深刻化する「逆テクハラ」も問題
一方で、ITを苦手とする上司が部下にIT関連の作業を丸投げする「逆テクハラ」も増加しています。何度も同じ説明を求めたり、システムの使い方を覚えようとしない態度も、度を越すと逆テクハラになってしまいます。
職場への深刻な影響
- 生産性の低下
⇒ ITスキルの差による業務の停滞 - 人間関係の悪化
⇒ デジタル世代 vs アナログ世代の対立構造 - 離職率の増加
⇒ テクハラを受けた従業員の退職 - 企業の法的リスク
⇒ 職場環境配慮義務の不履行による損害賠償請求
実際に、テクハラが原因で精神的な健康を害し、労災認定を受けるケースも報告されています。企業にとっては、従業員の管理責任が問われる重大な問題なんです。
テクハラを防ぐために今できること
テクハラの防止には、個人レベルと組織レベルの両方でのアプローチが必要です。まず大切なのは、「ITスキルの差は当然のこと」という認識を職場全体で共有することです。
個人でできる対策
- 思いやりのあるコミュニケーション
⇒ 相手のITスキルレベルに合わせた説明を心がける - 専門用語の使い分け
⇒ わざと難しい言葉を使わず、分かりやすい表現を選ぶ - サポートの姿勢
⇒ 「教える」のではなく「一緒に解決する」という気持ちで接する
企業が取るべき対策
- ITリテラシー研修の実施
⇒ 全従業員が業務に必要なスキルを身につけられる環境づくり - 相談窓口の設置
⇒ テクハラの相談を受け付ける専門窓口の設置 - メンター制度の導入
⇒ ITスキルの高い従業員が低い従業員をサポートする仕組み - 定期的な職場環境チェック
⇒ アンケートや面談によるテクハラの早期発見
🌈 ちょっと一息
大切なのは「できて当然」ではなく「一緒に成長していく」という職場文化。テクハラのない職場は、全員の生産性向上につながります
まとめ
テクハラは、デジタル化が進む現代社会で避けて通れない新しいハラスメントです。従来のパワハラとは異なり、立場に関係なく誰もが加害者・被害者になりうる点で、より複雑な問題といえます。
2025年現在、ITスキルの差は個人の努力だけでは埋められない部分も多く、企業としての組織的な取り組みが不可欠です。
「こんなこともできないのか」という一言が、同僚の心を深く傷つけているかもしれません。大切なのは、ITスキルの違いを「欠点」ではなく「多様性」として捉え、お互いを尊重し合える職場環境を作ることです。
テクハラの防止は、単なるハラスメント対策を超えて、全従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
まずは今日から、職場の同僚に対して、より思いやりのあるコミュニケーションを心がけてみませんか。小さな配慮の積み重ねが、テクハラのない働きやすい職場を実現する第一歩となるはずです。
→ 関連ブログ:『職場の「見えないいじめ」同僚からの陰湿ハラスメントの手口』