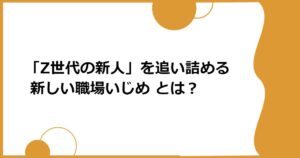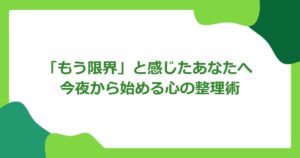副業ハラスメントって何?会社の理解不足が招く新しい対立
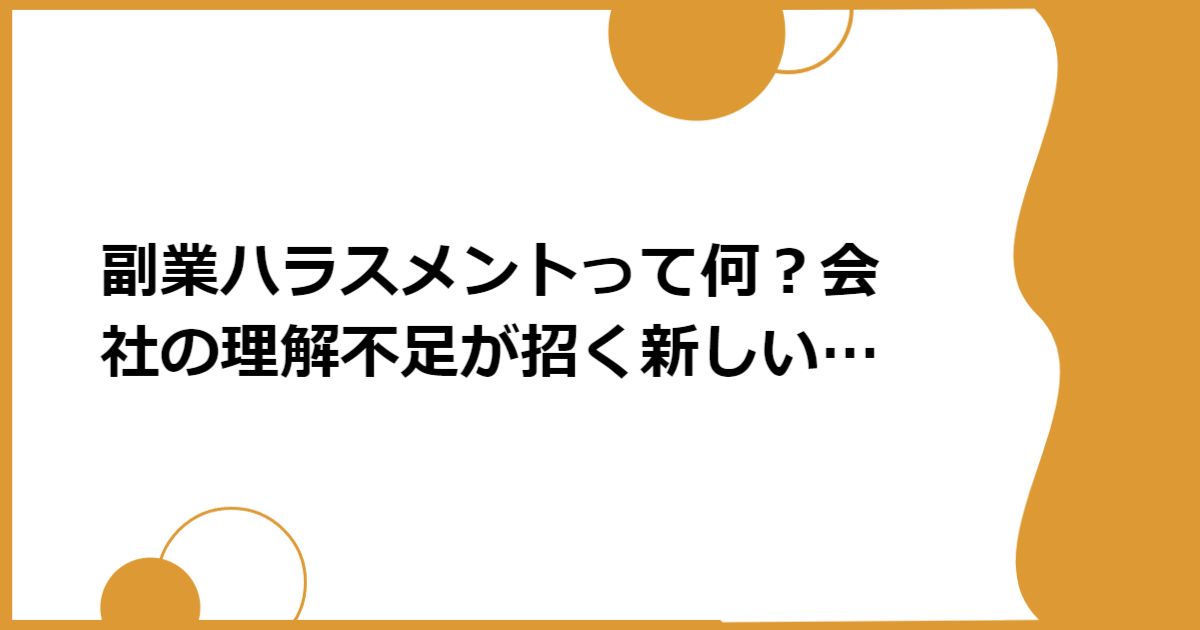
厚生労働省のガイドライン改定以降、
副業を認める企業が増える一方、SNSや相談窓口には「副業をきっかけにした職場トラブル」の声が寄せられるようになっています(ハラスメント全体の相談件数は増加傾向にある一方、副業に限定した公的統計は限定的)。
この記事で扱う「副業ハラスメント」は、まだ法律で明確に定義された用語ではありません。
しかし、副業を理由とした嫌がらせや不利益な扱いが、既存のハラスメント(パワハラ等)の枠組みで問題視されるケースが報告されています。
本記事では、こうした問題の背景や法的な観点を整理し、私たちにできる対処法を考えていきます。
副業をめぐる職場トラブルとは?
「副業ハラスメント」とは、社員が副業をしている、または希望していることを理由に、職場で精神的な苦痛を与えられたり、不利益な扱いを受けたりすることです。
報告されている相談事例
実際に、以下のようなご相談が寄せられることがあります。
- 上司から「副業をするなんて裏切りだ」「本業に集中しろ」などと叱責される
- 「副業なんてやってる暇があるなら残業しろ」と、過剰な業務を強要される
- 昇進や昇給の評価で「副業をやっている人は信用できない」といった不当な理由で評価を下げられる
なぜ?国の推進と現場の意識のギャップ
こうした問題の根底には、副業を推進する国の「働き方改革」と、現場に根強く残る旧来の価値観とのギャップがあります。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、モデル就業規則からも副業禁止規定を削除するなど、柔軟な働き方を後押ししています。
しかし、現場の管理職の意識が追い付いていない、という「会社の理解不足」がトラブルの温床となっています。
副業トラブルと法律の関係
では、副業を理由とした不利益な扱いは、法的にどのように考えられるのでしょうか。
会社の「副業禁止」はどこまで有効?
そもそも会社が従業員の副業を全面的に禁止するには、法律上、合理的な理由が必要です。ガイドライン等では、主に以下のようなケースが挙げられています。
- 業務への支障
⇒ 副業によって本業の業務に明らかに支障が出ている - 秘密保持義務
⇒ 本業で得た企業秘密が、副業で漏洩するリスクがある - 競業避止義務
⇒ 本業と競合する企業で働き、会社の利益を害する
これらの理由なく、一方的に副業を禁止したり、不利益な扱いをしたりすることは、違法と判断される可能性があります。
パワハラ防止法との関連
副業を理由に「やる気がない」と大勢の前で叱責したり、残業を強要したりする行為は、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)で定められたパワハラに該当する可能性があります。
🔑 ワンポイント
副業を理由とした不当な解雇や降格が争われた裁判例はまだ限定的ですが、少しずつ判例が積み重なってきています
もしトラブルに直面したら?
実際に副業をめぐるトラブルに直面した場合、冷静に行動することが大切です。
Step1:証拠を記録する際の法的注意点
客観的な証拠は、あなたの主張を裏付けるために非常に重要です。メールやチャットなどは全て保存しましょう。上司との会話を録音することも有効ですが、注意が必要です。
一般的に、自分自身が参加している会話の録音は、民事裁判では証拠として認められる可能性があります。最高裁判所の判例でも、被害保護のための録音が証拠として認められた例があります。
しかし、その証拠能力や合法性はケースバイケースで判断されるため、刑事事件や会社の就業規則との関係でリスクが生じる場合もあります。録音を検討する際は、事前に弁護士などの専門家に相談するのが安心です。
- 証拠として認められやすいケース
⇒ 相手からパワハラ発言を受けている自分を守るためなど、録音の必要性が高い場合 - 注意が必要なケース
⇒ 録音禁止が明示されている場所での録音や、他人同士の会話を盗聴する行為
Step2:具体的な相談窓口
一人で抱え込まず、可能な限り第三者に相談してください。具体的な相談先としては、以下のような公的機関があります。
- 総合労働相談コーナー
⇒ 全国の労働局や労働基準監督署内に設置されており、予約不要・無料で専門の相談員に相談できます - 労働条件相談ほっとライン
⇒ 平日の夜間や土日に、電話で気軽に相談できる窓口です
🌈 ちょっと一息
あなたの心と体の健康が最優先です。時には休職や転職も、自分を守るための大切な選択肢になります
まとめ
副業をめぐる職場トラブルは、働き方の過渡期である現代社会が生み出した問題です。
- 法的定義
⇒ 「副業ハラスメント」は法律用語ではないが、実態はパワハラに該当し得る - 会社の責任
⇒ 厚労省のガイドラインもあり、合理的な理由なく副業を禁止・制限することは許されない - 対処法
⇒ 証拠を記録し、労働局の「総合労働相談コーナー」など、社内外の適切な窓口に相談することが重要
副業をすることは、決して悪いことではありません。それは、あなたの人生を豊かにするための正当な権利です。会社の古い価値観や理解不足によって、その可能性を諦める必要はありません。正しい知識を身につけ、自分自身のキャリアと生活を守りましょう。
→ 関連ページ:『指導とパワハラの決定的な違いは何か』へ
→ 関連ブログ:『職場の人間関係で疲れた心のリセット術』へ