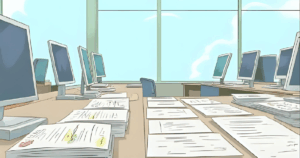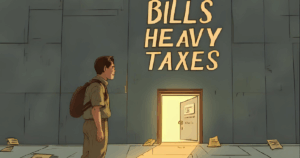マタハラとパタハラを同時に起こす「セット型」事例

職場でのハラスメントというと
「誰が」「誰に」
行ったかという形で語られることが多いですが、実際の現場では、一方だけが被害者で一方だけが加害者という単純な構図ではないケースもあります。
たとえば、女性社員が妊娠をきっかけに不利益な扱いを受ける「マタハラ」。そして、男性社員が育児休業や時短勤務を希望した際に冷たい目で見られる「パタハラ」。
この2つが同じ職場で同時に発生することがあります。
この記事では、そんな「セット型ハラスメント」と呼ばれる構造的な問題を、わかりやすく整理してみましょう。
「セット型」事例とは何か
「マタハラ」と「パタハラ」が同時に起きる職場には、ある共通点があります。
それは
「性別によって役割を固定的に見てしまう空気」
が職場全体に流れていることです。
典型的なパターン
- 女性が妊娠を報告したときに「これから大変ね」と仕事を外される
- 一方で、同時期に男性が育休を希望すると「男がそこまでしなくても」と言われる
- 育児を理由に勤務時間を調整した女性に対し「特別扱い」と陰口が出る
- その陰口を避けようと男性が家庭の負担を増やすと「家庭的すぎる」と揶揄される
- 上司が「誰かが残らないと回らない」と言いながら
- 結果的に育児をする男女双方に負担を強いる
🔑 ワンポイント
このような職場では、男女どちらも「普通の働き方」を選べない空気が生まれています
なぜ同時発生するのか
専門家によると、このような「セット型ハラスメント」は、組織文化と固定観念の合わせ技によって起こりやすいと指摘されています。
背景にある3つの要因
- 性別役割の固定化
- 「女性は家庭」「男性は仕事」という無意識の前提が根強く残っている
- 制度と現場のズレ
- 就業規則上は男女平等でも、現場では「使いにくい空気」が漂っている
- 上司・同僚の過剰な公平感
- 「誰かだけが得をしてはいけない」という思いが、結果的に支援を妨げてしまう
🌈 ちょっと一息
問題は個人の性格ではなく、職場全体の「空気」や「慣習」にあります
防ぐためにできること
マタハラ・パタハラを同時に防ぐには、「男女どちらかを守る」ではなく、働き方の多様性を受け入れる文化づくりが欠かせません。
今日からできる3つの視点
- 話しやすい雰囲気をつくる
- 妊娠や育児、家庭の事情などを安心して話せるミーティング文化を整える
- 制度を「使う側」の声を拾う
- 育休や時短勤務を実際に使った人の意見を定期的にフィードバックする
- 管理職自身が手本になる
- 上司が柔軟な働き方を実践することで、部下の行動への心理的ハードルが下がる
🔑 ワンポイント
「誰かのための配慮」ではなく「みんなのための制度」という発想に変えることが大切です
まとめ
今回は、「マタハラ」と「パタハラ」が同時に発生する「セット型」事例について紹介しました。
この記事のポイント
- マタハラとパタハラが同時に起きる背景には、性別役割への固定観念がある
- 組織文化の中で「公平さ」が過剰になると、支援をためらう空気が生まれる
- 防止のカギは、制度を使いやすくする文化と対話のある職場づくりにある
ハラスメントの形は一つではありません。
大切なのは、男女どちらの立場にも「安心して声を出せる環境」を整えることです。そして、誰かの経験が職場全体の改善につながるよう、やさしい対話を重ねていくことなんです。
→ 関連ページ:『セクハラ、モラハラ…心を蝕む攻撃の種類と実例』へ
→ 関連ページ:『あなたの職場は大丈夫?ハラスメントが蔓延する環境の特徴』へ