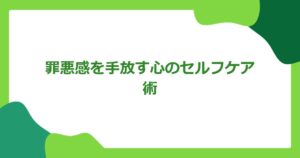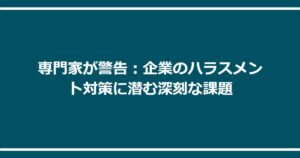【2025年法改正対応】「オワハラ」の巧妙な手口と見抜き方
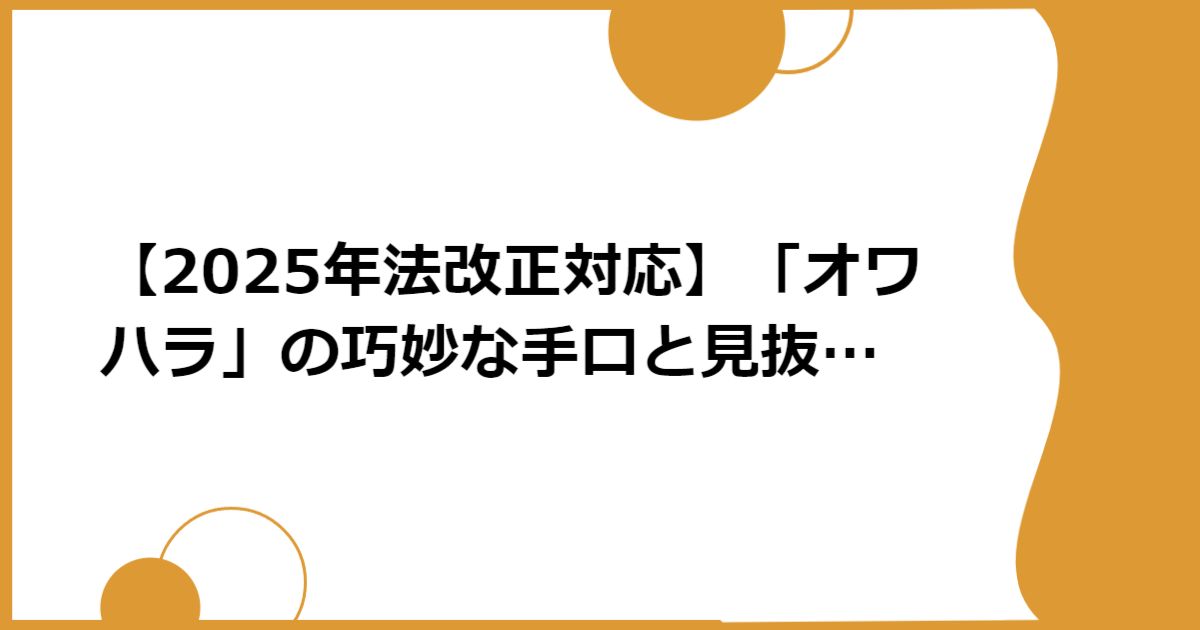
「内定を出すから、他社の選考は
辞退してほしい」
就職活動中にこんな要求を受けたことはありませんか?
これは「オワハラ(就活終われハラスメント)」と呼ばれる新しいタイプのハラスメントなんです。
現在は企業にとって努力義務に留まっていますが、厚生労働省では就活生へのハラスメント防止措置の義務化に向けた検討が本格化しており、この問題への注目度が急激に高まっています。今回は実際の事例を通じて、オワハラの巧妙な手口と対処法をお伝えします。
オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略で、企業が内定を出すことを条件に、他社の選考活動の中止や内定辞退を迫るハラスメント行為のことです。
オワハラが生まれる背景
1. 新卒採用の激化
⇒ 優秀な人材を獲得したいという企業の強い思いから、内定を出すことを条件に他社の内定辞退の強要や、就活を終わらせるように迫ることがハラスメント行為に該当します。
2. 人材確保への焦り
⇒ 少子化の影響で優秀な学生は企業同士の取り合いとなっており、「他社に取られる前に確保したい」という心理が働いています。
オワハラの4つの巧妙な手口【実例付き】
心理学的な分析によると、オワハラには以下の4つの傾向があることがわかっています。
1. 交渉型オワハラ
手口
その場で即断を迫る。
実例
面接後に複数の社員で学生を囲み、
「今ここで他社を断ってくれれば、すぐに内定を出します。どうですか?」
と選択の余地を与えない圧力をかけるケース。
2. 束縛型オワハラ
手口
スケジュールを束縛して他社を受けられなくする。
実例
他社の選考期間に被るように自社の内定者研修などイベントを被せて拘束をし、他社を受けにくくすることなどが該当します。
🔑 ワンポイント
「研修は必須参加です」と言われても、まだ正式な内定者でない場合は参加義務はありません
3. 同情型オワハラ
手口
人間関係を利用した心理的圧迫。
実例
「君のために特別枠を作ったんだ」
「人事部長が君を高く評価している」
など、断りにくい人間関係を作り上げるケース。
4. 脅迫型オワハラ
手口
恐怖心を煽って選択を強要。
実例
「今後、あなたの大学の後輩を採用しない」
など周囲へのいやがらせをほのめかすケース。
オワハラを見抜く5つのチェックポイント
即断を求められる
「今すぐ決めてほしい」
「明日までに返事を」
など、考える時間を与えないケース。
個室での面談を求められる
過去の就活ハラスメントの事件では、採用担当者が個室で1対1の面談を求めたりするケースが報告されています。
私的な連絡先を聞かれる
個人の携帯メールやSNSアプリで連絡を入れてくるような不適切な要求をしてきます。
内定承諾書の提出を急かされる
内定を出す前に内定承諾書を提出させ、他社へのアプローチを止めさせる行為は明確なオワハラです。
研修や懇親会への参加を強制される
内定者でもないのに「必須参加」と言われた場合は要注意です。
🌈 ちょっと一息
これらの行為は職業選択の自由を侵害する違法行為の可能性があります
オワハラを受けた時の対処法
1. その場では曖昧に対応する
無理に断ろうとせず、
「検討させていただきます」
「家族と相談して決めたいと思います」
など、一旦保留にしましょう。
2. 記録を残す
- 日時・場所・相手の名前
- 具体的な発言内容
- 同席者の有無
- メールやLINEのスクリーンショット
3. 信頼できる人に相談する
- 大学のキャリアセンター
- 家族や友人
- 厚生労働省の相談窓口
4. 法的知識を持つ
候補者が内定を承諾した時点で、会社と候補者の間に雇用契約が成立します。しかし、内定承諾前であれば法的な拘束力はありません。
まとめ
オワハラは就活生の職業選択の自由を不当に妨げる行為であり、度が過ぎると違法行為になります。現在、厚生労働省では就活生へのハラスメント防止措置の義務化に向けた検討が進められており、企業の意識も変わりつつあります。
重要なポイント
- オワハラは4つのパターンに分類される
- 見抜くためのチェックポイントを覚えておく
- 被害を受けたら記録を残し、信頼できる人に相談する
- 自分の権利を正しく理解することが大切
あなたには自由に企業を選ぶ権利があります。どんなに魅力的な企業でも、オワハラを行うような企業への入社は慎重に検討すべきでしょう。安心して就職活動を続けるためにも、正しい知識を身につけておくことが大切です。
→ 関連ページ:『次への一歩を踏み出す』へ
→ 関連ブログ:『会社の相談窓口が頼りにならない時、どうすればいい?』へ