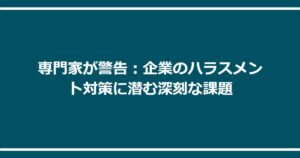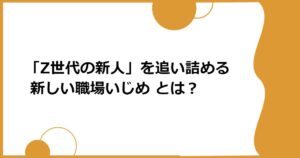職場の「独り言」はハラスメント?法的な境界線と企業の責任
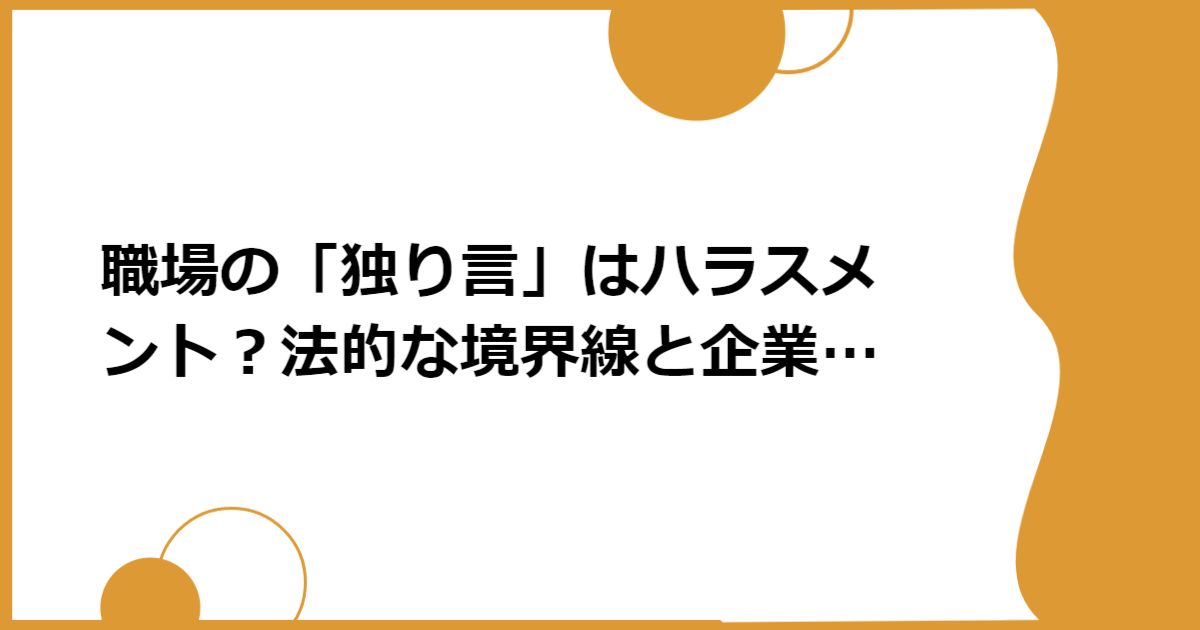
「あー、また間違えた」
「なんでこうなるんだよ…」
職場で繰り返される同僚の独り言。悪気がないのは分かっていても、毎日続くと集中できなくてつらい…。これは多くの職場で起こりうる、根深い問題です。
最近「独り言ハラスメント」という言葉を聞くことがありますが、これは法律で定められた正式なハラスメントの分類ではありません。
しかし、度を超えた独り言は、見過ごすことのできない「職場環境に影響を及ぼす要因」となる可能性があるんです。この記事では、その法的な境界線と、会社が負うべき責任について解説します。
「ハラスメント」ではない?でも見過ごせない職場環境への影響
まず知っておきたいのは、独り言がパワハラなどの法的なハラスメントに直接該当するケースは稀だということです。なぜなら、多くの場合、誰かを攻撃する意図がないためです。しかし、だからといって我慢すべき問題ではありません。
集中力を奪う「音のストレス」要因
継続的で過度な独り言は、周囲の従業員にとって深刻なストレス要因となり得ます。
- 思考の中断
⇒ 集中して作業している時に思考が何度も中断され、業務効率が著しく低下する - 精神的な疲労
⇒ 聞きたくない音を常に意識し続けることで、精神的に大きく疲弊してしまう
こうした状況は、個人の問題ではなく、職場全体の生産性に関わる重大な課題です。
法律上の根拠は?企業が負う2つの責任
では、会社に対して何も言えないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。ここに関わってくるのが、法律で定められた会社の重要な責任です。
① 労働契約法上の「安全配慮義務」
労働契約法第5条には、会社は従業員が安全で健康に働けるように配慮しなければならないという「安全配慮義務」が定められています。
過度な独り言によって従業員が精神的な苦痛を感じ、健康に働ける環境が損なわれていると判断された場合、判例によっては、職場環境の放置が安全配慮義務違反と認められる場合があります(事案ごとの判断です)。
② 労働施策総合推進法上の「防止措置義務」
さらに、2020年から施行されている「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」では、事業主にハラスメントを防止するための措置を講じることを義務付けています。
これには、ハラスメントが起きにくい良好な職場環境を維持する責任も含まれます。
🔑 ワンポイント
これら2つの法律に基づき、会社は「個人の問題」として放置せず、職場環境を改善する責任を負っているのです
会社と個人ができる具体的な対処法
この問題は、誰か一人を責めるのではなく、会社が主体となって環境を整え、お互いが歩み寄ることが解決の鍵となります。
会社に求められる対応
法律に基づき、会社は以下のような対応を検討することが望まれます。
- 実態の把握
⇒ 従業員アンケートやストレスチェックなどを活用し、職場環境の問題点を客観的に把握する - 物理的な対策・個別配慮
⇒ 集中作業用のブースを設けたり、パーティションを設置したり、状況に応じて席替えやイヤホンの使用を許可したりする - ルール作りと周知
⇒ 静粛な環境を保つためのガイドラインを作成し、研修などを通じて周知徹底する
もしあなたが悩んでいるなら
一人で抱え込まず、まずは会社に対して「職場環境の改善」を働きかけてみましょう。
- 上司や人事部へ相談する
⇒ 「独り言で集中できず困っている」と具体的に伝え、環境改善を求める - 記録を取っておく
⇒ いつ、どのような独り言で、業務にどんな支障が出たかをメモしておくと、相談の際に役立ちます
🌈 ちょっと一息
「ハラスメントだ」と個人を責めるのではなく、「働きやすい環境にしたい」という視点で相談するのがポイントです
まとめ
職場の独り言問題について、法的な観点から解説しました。
- 「独り言ハラスメント」は法律用語ではない
⇒ しかし、度を超えれば見過ごせない「職場環境に影響を及ぼす要因」です - 会社には2つの法的責任がある
⇒ 「安全配慮義務」とハラスメント「防止措置義務」に基づき、職場環境を整える責任があります - 解決の鍵は「環境改善」
⇒ 個人を責めるのではなく、会社が主体となって働きやすい環境を作ることが求められます
もしあなたが今、職場の独り言で深く悩んでいるなら、それは決して「あなたの我慢が足りない」からではありません。会社に相談し、働きやすい環境を求めることは、あなたの正当な権利です。
→ 関連ページ:『これって、もしかして?―あなたの心の声に答える―』へ
→ 関連ブログ:『職場の人間関係で疲れた心のリセット術』へ