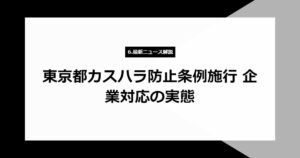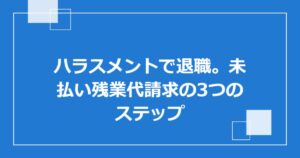職場の雑用、なぜ女性だけ?『ケアハラ』の実態と心の守り方
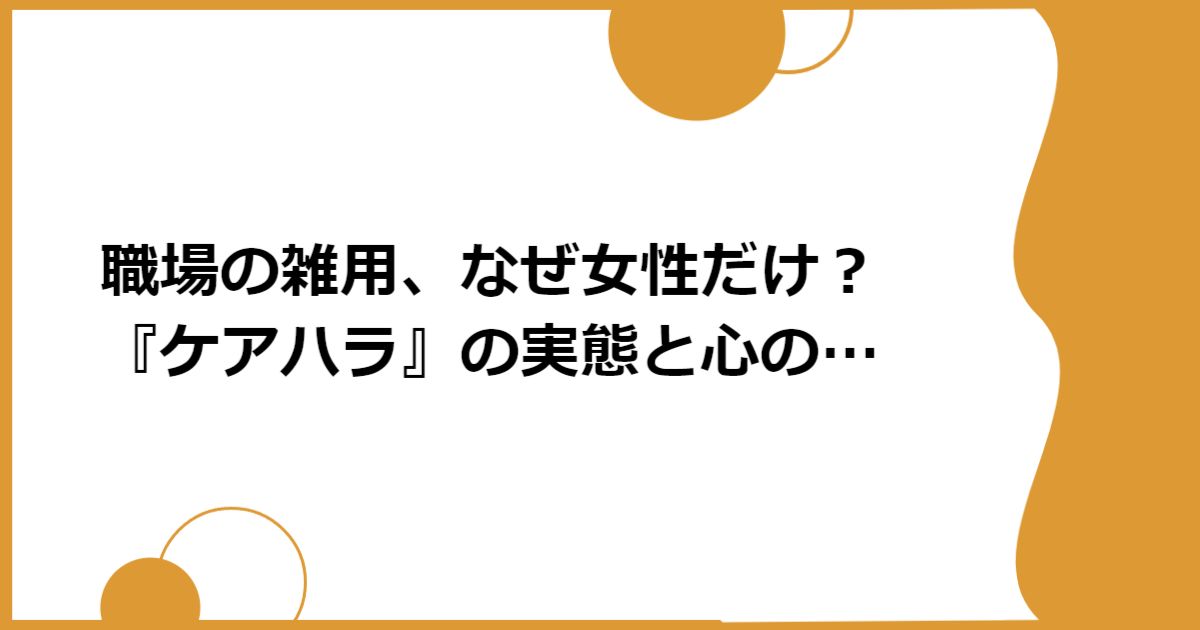
来客対応、電話が鳴った時、飲み会のセッティング…。
職場で誰かがやらなければいけない雑務が発生した時、なぜかいつも自分に声がかかる。そんな経験はありませんか。
「〇〇さん、お願いね」
「女の子だから、こういうの得意でしょ?」
そんな言葉と共に、本来の業務とは関係のない役割を押し付けられる。
断れば「協調性がない」と思われそうで、つい引き受けてしまうけれど、心の中ではモヤモヤとした気持ちが消えない…。
その不快感や理不尽さは、決してあなたの「気にしすぎ」ではありません。 それは
「ケアハラスメント(ケアハラ)」
と呼ばれる、立派なハラスメントの一つなんです。
この記事では、多くの人が無意識のうちに加害者にも被害者にもなってしまう「ケアハラ」の実態と、心をすり減らさずに自分を守るための考え方について、具体的に解説していきます。
それ、ケアハラです。ハラスメントになる「役割分担」の境界線
ケアハラスメントとは、本人の職務内容とは関係なく、性別、年齢、性格といった固定的なイメージによって「世話役(ケアする役割)」を一方的に押し付ける行為のことです。
ケアハラの具体的な事例
職場におけるケアハラには、下記のようなものが挙げられます。
- 来客時のお茶出しや、部署で飲むお茶の準備・片付け
- 部署内のゴミ捨てや給湯室、共有スペースの清掃
- 飲み会や社内イベントの幹事・お店選び・出欠確認
- 上司の昼食の買い出しや、クリーニングの受け取りといった私的な用事
- 「場の空気を和ませて」「みんなを励ましてあげて」といった感情的な役割の強要
もちろん、これらの行為自体が問題なのではありません。チームで分担を決めていたり、全員が納得の上で協力していたりするなら、それは円滑な職場運営に必要な業務と言えるでしょう。
「親切」と「ハラスメント」の境界線
では、どこからがハラスメントになるのでしょうか。 その境界線は、
「本人の能力や意欲とは無関係な、固定観念に基づく強要があるかどうか」
です。
🔑 ワンポイント
本人の能力や意欲ではなく『女性だから』『若いから』といった属性を理由に雑務を押し付けることが問題なんです
「女性は気配りができるから」
「若手はフットワークが軽いから」
といった無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)によって、特定の個人にだけ雑務が集中している状態は、非常に危険な兆候と言えます。
「些細なこと」では済まされない。ケアハラがもたらす深刻な影響
「お茶汲みくらいで大げさな」と感じる人もいるかもしれません。 しかし、この「些細なこと」の積み重ねが、働く人のキャリアと心に深刻な影響を与えてしまうんです。
通常業務の圧迫と正当な評価の阻害
雑務に費やす時間は、当然ながら本来の業務を行う時間から奪われます。その結果、時間内に仕事が終わらず残業が増えたり、集中して取り組むべき業務のクオリティが下がってしまったりする可能性があります。
「雑務はこなして当たり前」
という雰囲気の中では、その努力が評価されることはなく、結果的に不当な人事評価につながる恐れもあるんです。
専門性の軽視とモチベーションの低下
自分の専門スキルを磨き、キャリアを築くために会社にいるのに、「お茶汲み要員」として扱われることで、自分の専門性が軽視されていると感じてしまいます。
「この会社では、自分の能力は必要とされていないのかもしれない」
そんな無力感は、仕事へのモチベーションを著しく低下させる原因となります。
自己肯定感の低下と「諦め」の感情
ケアハラが常態化すると、被害者自身も
「それが自分の役割なんだ」
と無意識に思い込んでしまうことがあります。
「どうせ私がやるしかない」
という諦めの感情は、徐々に自己肯定感を蝕んでいきます。これは、他のより深刻なハラスメントが発生した際にも、「自分が我慢すればいい」と考えてしまう危険な心理状態につながりかねません。
🌈 ちょっと一息
あなたの価値は、お茶を淹れる上手さではなく、仕事の専門性にあるはずです
心をすり減らさない。「自分」を守るための3つのステップ
では、このような状況にどう向き合えばいいのでしょうか。 正面から
「それはハラスメントです!」
と対立するのではなく、まず自分を守るための考え方と、明日から実践できる小さな行動をご紹介します。
Step 1: 「私の仕事ではない」と心の中で線引きする
まず大切なのは、
「雑用をうまくこなせない自分が悪いんだ」
と自分を責めないことです。これはあなたの問題ではなく、職場の文化や体質の問題なんです。
心の中だけでも
「これは本来、私の専門業務ではない」
という線を引くことで、過度な責任感から自分を解放してあげましょう。
Step 2: 「できません」ではなく「今は難しい」と伝えてみる
いきなり「やりません」と強く断るのは勇気がいりますよね。そんな時は、
「(自分の通常業務を理由に)今は対応が難しい」
という形で伝えてみるのが有効です。
- 「申し訳ありません、今〇〇の作業で手が離せなくて…」
- 「急ぎの仕事を抱えておりまして、他の方にお願いできないでしょうか?」
- 「その件、〇時までには対応できるかと思いますが、お急ぎですか?」
このように、あくまで「仕事が忙しい」という客観的な事実を伝えることで、相手も無理強いしにくくなります。
Step 3: 「いつ」「何を」頼まれたか簡単な記録をつける
すぐに誰かに相談するつもりがなくても、簡単なメモを残しておくことをお勧めします。
「いつ、誰に、どんな雑務を頼まれたか」
を客観的に記録することで、
「気のせいじゃなかったんだ」
と自分自身の状況を冷静に把握できます。この記録は、もしもの時にあなたの心を支え、状況を説明するための大切な材料になるかもしれません。
まとめ
今回は、職場で起こりがちな
「ケアハラスメント」
の実態と、その影響、そして自分を守るための具体的なステップについて解説しました。
- 性別などの固定観念で雑務を強要するのは「ケアハラ」というハラスメントである
- 「些細なこと」と軽視されがちだが、キャリアや心に深刻な影響を与える
- 自分を責めず、小さな工夫で「心の防御壁」を築くことが大切
「お茶汲み」や「雑用」は、誰かがやらなければいけない仕事かもしれません。しかし、その負担が特定の属性を持つ人に偏るのは、決して健全な職場とは言えません。
あなたの価値は、性別や年齢で決められるものではありません。もし、あなたが今、ケアハラによって専門業務に集中できず、心がすり減るような思いをしているのなら、それは決して「当たり前」のことではないと知ってください。
一人で抱え込まず、まずはこの記事で紹介したような心の守り方を試してみてはいかがでしょうか。
→ 関連ページ:『セクハラ、モラハラ…心を蝕む攻撃の種類と実例』へ
→ 関連ページ:『もう迷わない。目的別の最適な相談先マップ』へ