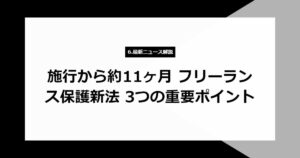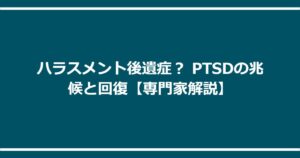ブラハラとは?「B型は自己中」がパワハラになる理由
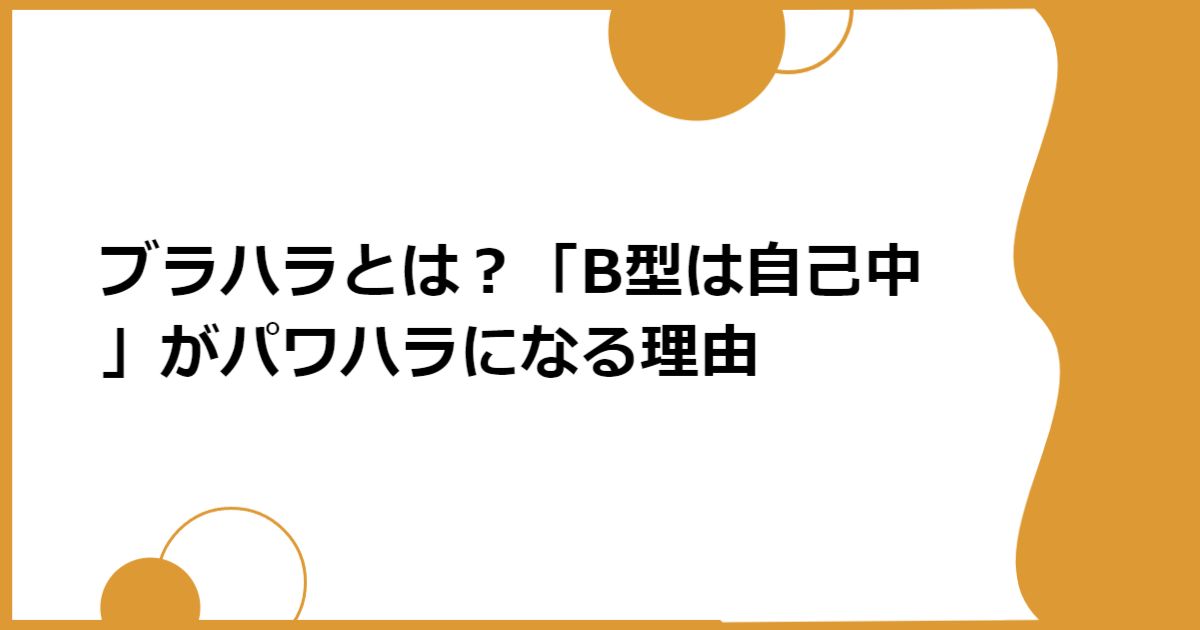
飲み会や自己紹介の場で、
誰もが一度は盛り上がったことのある「血液型の話」。
「A型だから神経質」
「O型は大雑把」
などといった会話は、コミュニケーションの一環として楽しまれることもあります。
しかし、その会話が一方的な決めつけに発展し、不快な思いをした経験はありませんか。
職場で問題になるのは、怒鳴るような分かりやすいパワハラだけではありません。
こうした日常会話に潜む「決めつけ」も、人の心を深く傷つけ、「ブラッドタイプ・ハラスメント(ブラハラ)」というハラスメントになり得るんです。
この記事では、なぜ科学的根拠がない(薄い)にも関わらずブラハラが起きてしまうのか、その心理的な背景と、うんざりした時の心の守り方を解説します。
「冗談だよ」では済まされない。ブラハラがハラスメントになる理由
「血液型の話で目くじらを立てるなんて」
と思う人もいるかもしれません。しかし、その「冗談」が個人の尊厳を傷つけ、安心して働ける環境を脅かすのであれば、それはもう冗談では済まされません。
血液型という自分では変えられない属性で個人の能力や人格を判断するのは、年齢で能力を決めつけるエイハラ(エイジハラスメント)や、性別で役割を押し付けるセクハラと、構造的には同じ問題を抱えています。
職場におけるブラハラの具体例
- 業務の割り振り
⇒ 「A型は真面目だから、この細かい作業をお願いね」 - 人事評価
⇒ 「B型は自己中心的だから、チームリーダーには向いていない」 - 意見の否定
⇒ 「AB型は気分屋だから、君の意見はまた変わるんだろう?」
世界的に見ても、性格と血液型を関連付ける考え方は日本など一部の国に限られており、科学的な研究でもその関連性は繰り返し否定されています。
🔑 ワンポイント
個人の尊厳を傷つけ、職場の環境を悪化させる言動は、たとえ悪気がなくてもハラスメントになり得ます
なぜ信じてしまうのか?ブラハラが生まれる3つの心理的メカニズム
科学的な根拠がないにも関わらず、なぜ多くの人が血液型と性格を結びつけてしまうんでしょうか。そこには、人の思考のクセや心理が関係しています。
- 認知バイアス(思い込み)の罠
⇒ 誰にでも当てはまりそうな曖昧な性格特徴を「まさに自分のことだ」と思い込んでしまう「バーナム効果」や、自分の信じたい情報ばかりを集めてしまう「確証バイアス」が働き、一度信じるとますますその考えが強化されてしまうんです - コミュニケーションの「潤滑油」という勘違い
⇒ 相手のことがよく分からない時、「〇〇型」というテンプレートに当てはめることで、手っ取り早く相手を理解した気になれます。
特に雑談のネタに困った時、便利な共通言語として使われやすい側面があります - 責任転嫁の便利な道具
⇒ 仕事上のミスや人間関係の不和を、相手の性格や能力の問題としてではなく、「血液型のせいだから仕方ない」と結論づけることで、思考を停止させ、安易な納得感を得ようとする心理も働きます。
これは、論理的に相手を追い詰めるロジハラとは対照的に見えますが、「相手を単純化して分かった気になる」という点では、人の尊厳を軽視する危険な思考の入り口になり得ます
「またその話…」とうんざりした時の、心の守り方
職場でブラハラに遭遇した際に、角を立てず、かつ自分の心を守るための具体的な対処法をご紹介します。
ユーモアで受け流す
「よく言われます!でも、実は掃除は苦手なO型なんです(笑)」
のように、あえてステレオタイプに乗っかりつつ、自分の個性で返すことで、相手に
「この人はテンプレ通りじゃないんだな」
と気づかせるきっかけになります。
話題をそっと転換する
「血液型の話も面白いですけど、〇〇さん、週末はどこか出かけられたんですか?」と、相手のプライベートな話題(もちろん差し支えない範囲で)に切り替えることで、自然に会話の流れを変えることができます。
「私」を主語にして正直に伝える(Iメッセージ)
もし、あまりにしつこい場合や、業務に支障が出そうな場合は、
「すみません、私、血液型で性格を判断されるのはあまり得意じゃなくて…」
と、「私」を主語にして自分の気持ちを正直に伝えてみるのも一つの方法です。
🌈 ちょっと一息
あなたの感情はあなただけのもの。不快に思うのは、決してわがままではありません
まとめ
今回は、日常に潜む「ブラハラ」について、その背景と対処法を解説しました。
- ブラハラは、科学的根拠のない「決めつけ」によるハラスメントである
- 認知バイアスや、コミュニケーションの潤滑油として使われやすい背景がある
- 相手を傷つけず、自分の心を守るための「かわし方」を知っておくことが大切
目に見えるパワハラや、PCが苦手なことを責めるテクハラなど、ハラスメントには様々な形がありますが、その根底にあるのは「個人への尊重の欠如」です。
血液型という4つの箱に無理やり人を入れるのではなく、一人ひとりの個性そのものに目を向けること。それが、誰もが心地よく働ける職場環境の第一歩と言えるでしょう。
→ 関連ページ:『ハラスメントの境界線を見極めるには』へ
→ 関連ブログ:『職場の「見えないいじめ」同僚からの陰湿ハラスメントの手口』