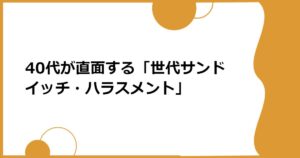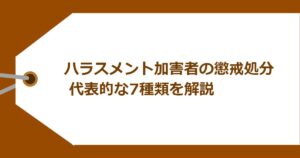ハラスメント加害者が「軽い処分」で済む本当の理由
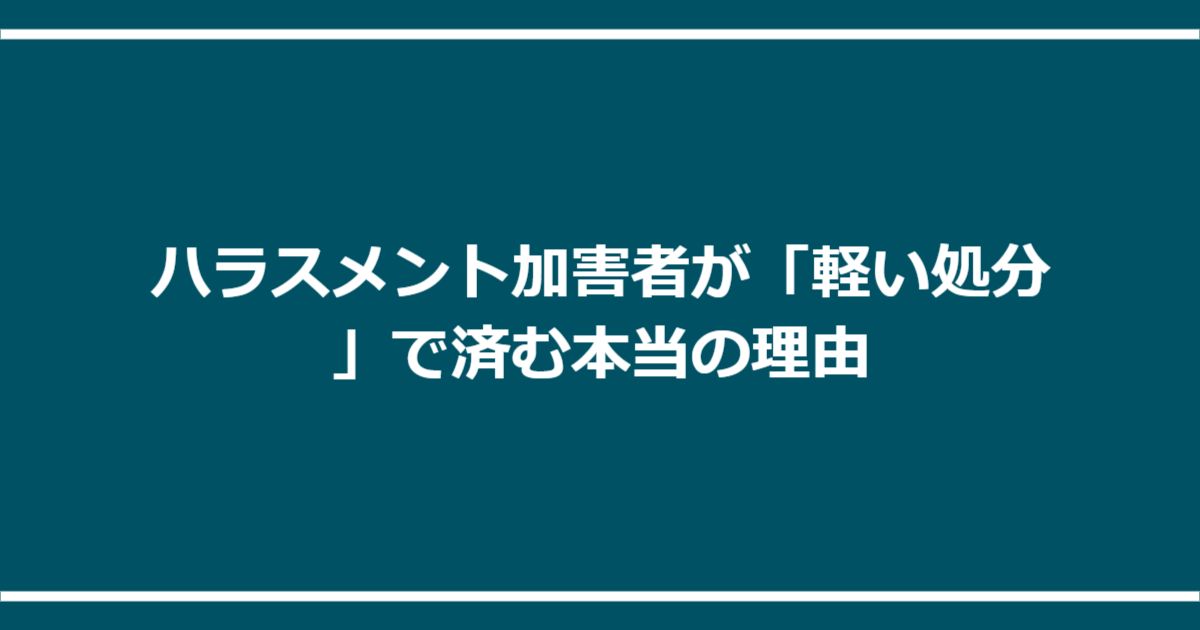
あれだけ酷いパワハラを受けたのに、
「なぜあの人は口頭注意だけで済んでいるの…?」
「会社は私の訴えを真剣に聞いてくれなかった。結局、加害者を守るんだ…」
勇気を出してハラスメントを告発したにも関わらず、加害者に下された処分の軽さに、愕然とし、深く絶望した経験はありませんか。
会社がまるで加害者の味方をしているかのように見えるのには、実は表からは見えにくい、企業の「本音」と法的な構造問題が隠されています。
この記事では、ハラスメント加害者が軽い処分で済んでしまいがちな、被害者にとっては理不尽極まりない「本当の理由」を解説します。
※この記事は、人事に関する専門的な解説書や公開されている複数の情報を基に、ハラスメント問題の裏側で何が起きているのかを、読者の皆さまに分かりやすくお伝えすることを目的に再構成したものです。
「証拠」の壁と「懲戒処分の重さ」という法的リスク
会社が加害者に重い処分、特に「懲戒解雇」といった最も重い罰を下せない最大の理由は、法的なリスクです。
会社が恐れる「不当解雇」での敗訴リスク
実は、日本の法律では従業員を解雇するためのハードルは非常に高く設定されています。
客観的で明白な証拠が不十分なまま厳しい懲戒処分を下すと、後に加害者本人から
「処分が重すぎる」
「不当解雇だ」
と訴訟を起こされた場合、会社側が敗訴してしまうリスクがあるんです。
人事担当者が直面する「証拠の壁」
- 「言った言わない」の水掛け論
⇒ 密室での暴言など、当事者しかいない状況では客観的な証拠がなく、事実認定が困難を極める - 証言の信憑性
⇒ 被害者と同僚の証言があっても、「個人的な好き嫌いが影響しているのでは?」と加害者側から反論される - 「指導」との線引きの難しさ
⇒ 加害者が「業務上必要な指導の一環だった」と主張した場合、その悪質性を客観的に証明する必要がある
🔑 ワンポイント
人事部としては「クロだと確信」していても、裁判で勝てるだけの客観的証拠がなければ、重い処分に踏み切れない。これが第一の現実です
加害者が「稼げる従業員」である場合の経営判断
非常にデリケートで、決してあってはならないことですが、加害者の処分を決定する際に「経営的な判断」が影響してしまうケースも、残念ながら存在します。
「事業上の損失」との天秤
もし、ハラスメントの加害者が…
- 高い営業成績を上げているエース
- その人にしかできない専門スキルや人脈を持っている
- 多くの部下を抱えるキーパーソンである
といった場合、会社がその従業員を失うことによる
「事業上の損失」
と、ハラスメント問題を厳正に処分することを、経営陣が天秤にかけてしまうことがあるんです。
もちろん、これはコンプライアンス上、決して許されることではありません。
しかし、短期的な利益を優先する企業体質の場合、「厳重注意」や「他部署への異動」といった軽い処分で幕引きを図ろうとする力が働きやすいのが実情です。
🌈 ちょっと一息
これは、従業員の心身の安全よりも、会社の利益を優先する、極めて不誠実な経営判断と言わざるを得ません
「軽い処分」で終わらせないために、被害者ができること
では、被害者は、こうした理不尽な現実を前に、ただ泣き寝入りするしかないのでしょうか。
決して、そんなことはありません。会社を正しく「動かす」ために、被害者が戦略的に取るべき行動があります。
感情的な訴えから、「法的な主張」へ
「辛かったです」
「酷いことを言われました」
という感情的な訴えはもちろん重要です。しかし、人事を動かすには、それに加えて
「会社の法的リスク」
を冷静に認識させることが非常に効果的です。
相談時に伝えるべき「キーワード」
- 「会社の安全配慮義務に違反している可能性があります」
⇒ 会社には、従業員が安全で健康に働ける環境を維持する義務があります。これを怠っている、と指摘します - 「このままでは心身の不調により、通常業務の継続が困難です」
⇒ あなたが休職や退職に至った場合、会社が安全配慮義務違反で訴えられるリスクを示唆します - 「これまでの経緯は、すべて客観的な記録として残してあります」
⇒ あなたが感情的になっているのではなく、冷静に証拠を積み上げていることを伝えます
「客観的な記録」こそが最大の武器
上記の主張を裏付けるために、やはり客観的で詳細な記録の存在が不可欠になります。
- いつ、どこで、誰に、何をされた(言われた)か
- その時の状況と、周りに誰がいたか
- あなたがどう感じ、どんな影響(体調不良、ミスなど)が出たか
これらの具体的な記録を提示されると、人事担当者は「これは単なる感情論ではない。法的リスクが高い案件だ」と認識し、対応のレベルを上げざるを得なくなります。
まとめ
今回は、人事に関する専門的な視点から、ハラスメント加害者の処分が軽くなりがちな理由と、その対処法について解説しました。
この記事のポイント
- 会社は、加害者から「不当処分」で訴えられる法的リスクを恐れている
- 加害者が会社にとって有益な人材である場合、経営判断が影響することがある
- 対処法は、感情的な訴えに加え、「客観的な記録」に基づき「会社の安全配慮義務違反」を冷静に主張すること
会社が加害者を守っているように見える背景には、こうした被害者には到底納得できない、しかし現実として存在する論理があります。
しかし、その現実を知ることで、あなたはより戦略的に、かつ冷静に自分の権利を主張し、会社を動かすことができるようになります。
理不尽な処分に諦める必要はありません。この記事が、あなたの正当な主張を通すための「知識」という、心強い味方になることを願っています。
→ 関連ページ:『証拠を集める ―未来のあなたを助ける武器―』へ
→ 関連ページ:『会社を動かすための、正しい報告ルートと手順』へ