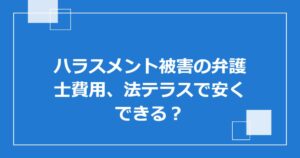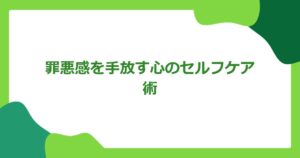カウンセラーが警告:相談窓口の『見えない落とし穴』
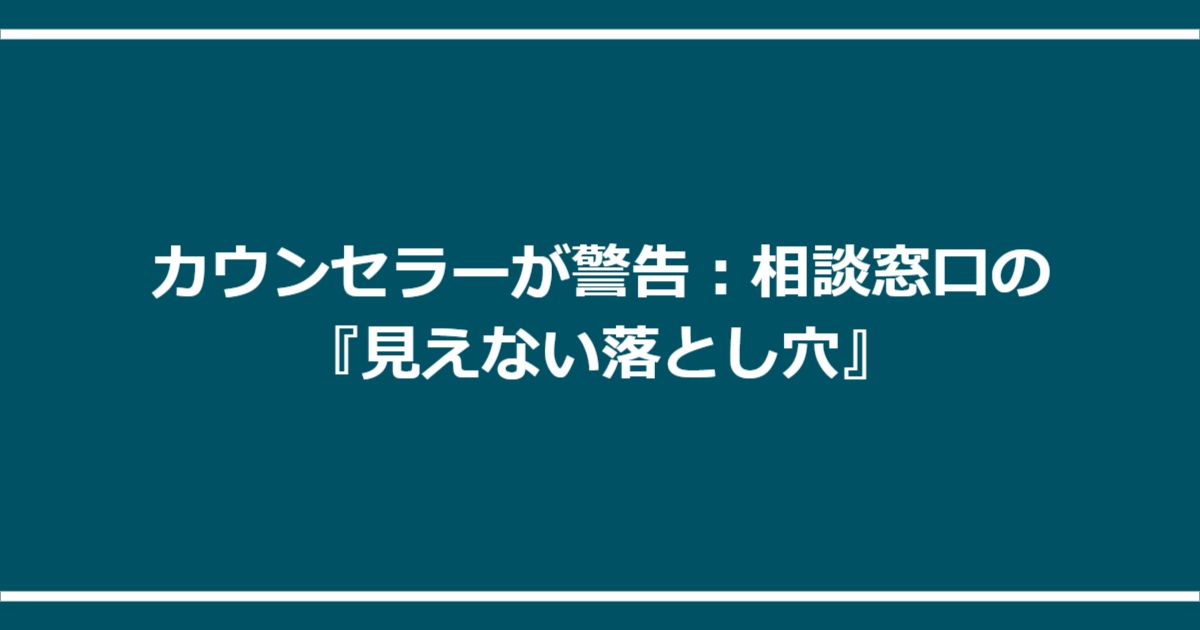
2022年4月、中小企業にも
ハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。
企業の82.9%が相談窓口を設置し、対策は着実に進んでいるように見えます。しかし、ハラスメントカウンセラーなど専門家の間では「設置すれば安心」という認識に対する深刻な懸念が広がっています。
実は、相談窓口の運営には多くの
「見えない落とし穴」
が潜んでおり、適切に対応できていない企業では、むしろ問題を悪化させてしまうケースが後を絶ちません。今回は、ハラスメントカウンセラーが指摘する相談窓口の深刻な問題と、その対策について解説します。
最大の落とし穴:認知度の致命的なギャップ
ハラスメントカウンセラーが最も危惧しているのが、企業側の認識と従業員の実態との大きなギャップです。
「設置したつもり」と「知らない現実」
厚生労働省の調査によると、企業の82.9%が「相談窓口を設置している」と回答しています。ところが、従業員側に聞くと「自社に相談できる窓口が設置されている」と答えたのはわずか45.5%でした。
この数字が示すのは、半数以上の従業員が相談窓口の存在すら知らないという深刻な現実です。
専門家が指摘する認知度低下の原因
周知方法の不備
- 就業規則に記載しただけで終わっている
- 新入社員研修で一度説明しただけ
- 社内イントラネットの奥深くに掲載されている
アクセスしにくい環境
- 人事部内に設置され、利用しにくい雰囲気
- 相談方法が限定的(電話のみ、メールのみなど)
- 営業時間が限定されている
信頼性への疑問
- 相談窓口担当者の専門性が不明
- プライバシー保護への不安
- 会社側の本気度に対する疑念
🔑 ワンポイント
窓口があることを知らなければ、相談することはできません
情報漏洩リスク:相談者を裏切る最悪のパターン
ハラスメントカウンセラーが最も警戒するのが、相談窓口での情報漏洩問題です。
実際に起きている深刻な事例
パワハラ相談窓口設置後の課題調査
最も多い問題として「相談者の情報漏洩」が挙げられました。具体的には以下のようなケースが報告されています。
勝手な事実確認による情報漏洩
ある管理職が部下からの嫌がらせを相談した際、担当者が相談者の了解を得ずに該当部下に事実確認を行った結果、あっという間に職場中に管理職が相談したことが知られてしまい、問題がこじれた事例。
相談内容の社内流出
- 相談内容が上司や人事に筒抜けになる
- 「誰が相談したか」が加害者に伝わる
- 社内で噂として広まる
情報漏洩が引き起こす深刻な二次被害
専門家によると、情報漏洩は被害者に以下のような深刻な影響を与えるといいます。
- 報復の恐れ
⇒ 相談したことで加害者から報復される - 職場での孤立
⇒ 「告げ口した人」として扱われる - 心理的ダメージ
⇒ 「誰も信用できない」という状態に陥る - 離職率の増加
⇒ 相談環境が用意されているにも関わらず、被害者が「退職」によって事態を収束させる
🌈 ちょっと一息
一度失った信頼を回復するのは非常に困難です
担当者のスキル不足が招く「善意の二次被害」
ハラスメントカウンセラーが指摘するもう一つの深刻な問題が、相談窓口担当者の専門知識不足です。
よくある「善意の対応」が裏目に出るパターン
詰問調の聞き取り
- 「なぜその場で逃げなかったの?」
- 「あなたにも問題があったのでは?」
- 「考えすぎではないか?」
加害者擁護の発言
- 「○○さんがいなくなったら仕事が回らない」
- 「会社のことも考えてほしい」
- 「そんな人には見えないけど…」
不適切な慰め
- 「あなたが優秀だから、将来を考えて言ったのでは」
- 「男性(女性)はみんなそのようなもの」
専門知識がない担当者の危険性
ハラスメントカウンセラーは、心理学の心得のない人が安易にカウンセリングを行うことの危険性を強く警告しています。
- 心の傷を広げるリスク
⇒ 不用意な発言で被害者の心をさらに傷つける - 問題の矮小化
⇒ ハラスメントの深刻さを軽視してしまう - 法的リスクの見落とし
⇒ 適切な対応を取れず、企業の責任問題に発展
相談しても「解決しない」という絶望
専門家が最も憂慮するのが、相談窓口に期待を持って相談した被害者が「解決しない」という絶望を味わう現実です。
「解決しない」相談窓口の実態
Job総研が2023年4月に発表した「2023年 ハラスメント実態調査」では、衝撃的な結果が明らかになりました。
- 相談環境が用意されているにも関わらず、誰にも相談しない被害者が多数
- 被害者の68.7%が「解決はないと思う」と回答
- 被害経験者の82.2%が退職を経験・検討
解決しない理由の深層
行為者の問題
- 行為者がパワハラをしている自覚がない(53.5%)
- 調査の結果パワハラの事実はないと判定されたが、被害者がパワハラを感じている(28.9%)
- 行為者が重要ポストにあるため異動などの措置ができなかった(21.4%)
システムの問題
- 事実確認の方法が不適切
- 再発防止策が機能していない
- アフターフォローが不十分
専門家が提案する「機能する相談窓口」の条件
ハラスメントカウンセラーは、真に機能する相談窓口には以下の条件が不可欠だと指摘しています。
専門性の確保
適切な担当者の選定
- ハラスメント相談員の資格を持つ担当者
- 心理学やカウンセリングの基礎知識
- 関連法律への理解
継続的な教育・研修
- 相談対応スキルの向上
- 最新の法令・制度への対応
- セカンドハラスメント防止の徹底
プライバシー保護の徹底
情報管理体制の構築
- 相談内容の厳重な管理
- アクセス権限の限定
- 情報漏洩防止策の徹底
相談者の同意なき行動の禁止
- 事実確認前の必ず相談者の同意取得
- 調査範囲の明確化
- 結果報告の適切な実施
多様なアクセス方法の提供
相談しやすい環境作り
- 対面、電話、メール、オンラインなど複数の相談方法
- 匿名での相談受付
- 24時間対応可能な体制
外部専門機関との連携
多くの専門家が推奨するのが、外部の専門機関との連携です。社内だけでは限界がある場合、外部のハラスメントカウンセラーや法律事務所に委託することで、より専門的で中立的な対応が可能になります。
まとめ
ハラスメント相談窓口の設置は、単なる法的義務ではなく、従業員の心と体を守るための重要な仕組みです。しかし、「設置すれば安心」という認識は大きな間違いです。
ハラスメントカウンセラーなど専門家が警告する「見えない落とし穴」は、企業の善意すら被害者をさらに傷つける危険性を示しています。認知度の低さ、情報漏洩リスク、担当者のスキル不足、そして根本的な解決力の欠如—これらの問題を放置したまま相談窓口を運営することは、被害者の信頼を裏切る行為に他なりません。
真に機能する相談窓口を作るためには、専門性の確保、プライバシー保護の徹底、そして継続的な改善が不可欠です。必要に応じて外部の専門機関との連携も検討し、被害者が安心して相談できる環境を整備することが、企業の責務といえるでしょう。
相談窓口は「作って終わり」ではありません。常に被害者の視点に立ち、専門家の知見を活用しながら、本当に頼れる存在へと育てていくことが求められています。
→ 関連ページ:『もう迷わない。目的別の最適な相談先マップ』へ
→ 関連ブログ:『産業医との面談時、何を話せばいい?』へ